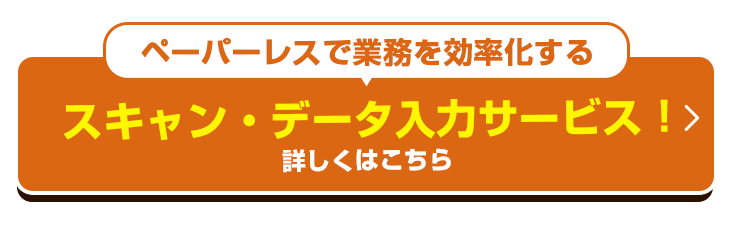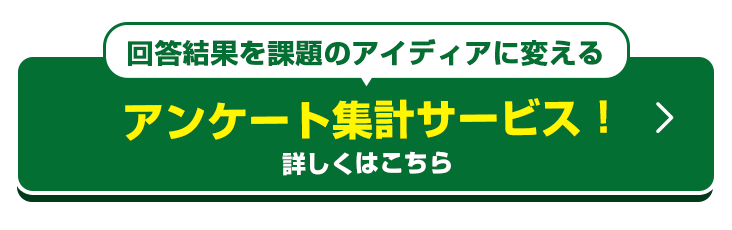データ入力の内容とは?社内作業するときの注意点と対策
多くの企業にとって、顧客情報や販売データ、在庫管理などのデータ入力作業は日常業務の一環として、業務効率の向上や企業の成長に欠かすことはできません。
しかし、社内でデータ入力を行う場合、リスクを把握しておかなければ業務効率の低下といったリスクを伴うことがあるため、注意が必要です。
そこで本記事では、データ入力の仕事内容と社内で作業する際の注意点やデータ入力効率化の方法について解説するので、データ入力作業の効率化に悩んでいる方はぜひ参考にしてください。
データ入力の仕事内容
データ入力では、主に以下のような業務を取り扱います。
- 文字入力
- 名刺入力
- ページ入力
- アンケート入力
- データ集計・グラフ化
- スキャニング など
近年ではDX化推進の影響もあり、紙資料のデータ化に対するニーズが高まっています。
また、データ入力だけでなく、データの整理、さらにはアンケートデータの集計やグラフ化なども活発に行われています。
データ入力の仕事を社内で行うときの注意点
社内でデータ入力する場合、主に3つの点に注意が必要です。
- 入力精度に対する不安
- 生産性が低下する
- 人件費がかかる
それぞれの注意点について、詳しく解説します。
入力精度に対する不安
データ入力には、整合性など高い精度が求められます。
入力ミスやデータの不整合が生じた場合、その後の業務や意思決定に支障をきたす可能性があるので注意が必要です。
また、不正確なデータは顧客対応や財務報告において重大な問題を引き起こす可能性があります。
エラーチェックや二重入力などの対策を講じることが求められますが、これらの対策にもコストと時間がかかるため、効率的な入力プロセスの確立が重要です。
生産性が低下する
データ入力作業は反復的で時間がかかるため、社員の生産性を低下させる要因となります。
特に大量のデータを扱う場合、一日の大部分が入力作業に費やされ、他の重要な業務に割ける時間が減少します。
この生産性の低下は、全体的な業務効率やプロジェクトの進行に悪影響を与えることがあります。
自動化ツールや効率的な入力システムの導入を検討することで、作業時間の短縮と生産性の向上を図ることができます。
人件費がかかる
データ入力には多くの人手が必要であり、その分の人件費コストが発生します。
特に正確な入力を維持するためには、訓練されたスタッフを配置する必要があり、これがさらにコストを増加させます。
また、入力ミスの修正や確認作業にも追加の労働力と時間が必要です。
これらのコストを抑えるためには、データ入力の効率化や自動化、あるいはアウトソーシングの検討が有効な手段となります。
関連記事:データ入力代行業者とは?料金相場やメリットを徹底解説
データ入力作業を効率化するには?
データ入力作業を効率化するには、次の3つの対策が考えられます。
- データ入力用スタッフの雇用
- データ入力ツールの使用
- データ入力をアウトソーシングする
それぞれの対策の具体的な内容について、以下で解説します。
データ入力用スタッフの雇用
データ入力作業の効率化のために、専任のデータ入力スタッフを雇用することは有効な手段です。
専門のスタッフは、データ入力に特化したスキルと経験を持っているため、一般の従業員に比べて正確かつ迅速に作業を行うことができます。
さらに、専任スタッフのトレーニングや研修を定期的に実施することで、入力精度やスピードの向上が期待できるでしょう。
また、データ入力のプロセスを標準化し、業務手順を明確にすることで、スタッフ間のばらつきを減らし、一貫した品質を保つことができます。
ただし、専任スタッフの雇用には人件費がかかるため、費用対効果を十分に検討し、業務量や作業内容に応じた適切な人員配置を行うことが重要です。
データ入力ツールの使用
データ入力ツールの使用は、効率化のための強力な手段です。
スキャナやOCR(光学文字認識)ソフトウェアを利用することで、手作業の入力を大幅に削減できます。
これにより、入力ミスの発生を防ぎ、作業のスピードを向上させることができます。
また、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を導入することで、繰り返しの多いデータ入力作業を自動化し、人間の介入を最小限に抑えることが可能です。
さらに、クラウドベースのデータ管理システムを使用することで、リアルタイムでのデータアクセスと共有が容易になり、チーム全体の協働作業がスムーズに進行します。
ツールの導入には初期投資が必要ですが、長期的には作業時間の短縮とコスト削減につながり、全体的な業務効率を大幅に向上させることができます。
データ入力をアウトソーシングする
データ入力作業をアウトソーシングすることも、効率化の有効な手段です。
専門の外部業者に業務を委託することで、社内リソースを他の重要な業務に集中させることができます。
アウトソーシング業者は高度な入力スキルと専用の設備を持っているため、迅速かつ正確にデータを処理することができます。
また、業務量の変動に柔軟に対応できるため、ピーク時の負荷を軽減することが可能です。
さらに、外部業者との契約により、データのセキュリティ対策や品質保証が確保されるため、信頼性の高いサービスを受けることができます。
しかし、アウトソーシングにはコストがかかるため、信頼できる業者の選定と適切な契約条件の設定が重要です。
また、業者とのコミュニケーションを密に保ち、業務内容や進捗状況を定期的に確認することで、アウトソーシングの効果を最大化することができます。
関連記事:これから依頼される方必見!データ入力代行会社の選び方!
関連記事:データ入力を外部委託する際は「精度の高さ」に注目を!
データ入力でお困りならプロセス・マネジメントまで
データ入力に関するお悩みは、プロセス・マネジメントの「電子化・データ入力サービス」にお任せください。
紙媒体の資料や手書きの書類を迅速かつ正確にデジタル化し、データベースに入力します。
高度なデータクリーニング技術で不正確なデータや欠損データを修正・補完し、信頼性の高いデータを提供。
また、チームは個人情報の保護に精通している個人情報保護士で構成されており、プライバシーマークやDXマークも取得済みであるなど、セキュリティ対策を徹底的に行うことで、個人情報を厳重に保護しています。
業務効率を大幅に向上させるためのプロフェッショナルなサービスを、ぜひご利用ください。
まとめ
データ入力を社内で行うと、正確性や生産性の低下、人件費の増加などのリスクが伴います。
これらのリスクを軽減するためには、専門スタッフの雇用やデータ入力ツールの導入、アウトソーシングの活用が有効です。
特にアウトソーシングは、コスト削減や業務効率化に大きなメリットがあります。
信頼できるサービスを利用することで、データ入力業務の負担を軽減したいとご検討中の方は、ぜひプロセス・マネジメントにご相談ください。
データ入力の効率化と安全性を確保するために、最適な方法をご提案させていただきます。
データ入力のミスにお困りの企業様必見!入力ミスを回避する方法を解説
顧客リストや取引先リスト、取り扱っている製品リストなどの作成・更新する作業を自社で行っている企業は少なくありません。
しかし、入力項目が膨大な量だった場合はミスが生じやすく、その結果として業務にさまざまな影響を及ぼす可能性があります。
そこで本記事では、データ入力のミスが多くて困っているという企業様に向けて、入力ミスを減らすためのポイントや対処法をご紹介します。
データ入力でミスが起きる原因
データ入力でミスが生じる主な原因は、以下の3点が考えられます。
- ヒューマンエラーによる入力ミス
- データ入力のマニュアルが確立されていない
- 入力したデータのチェック体制がない
それぞれの原因を詳しく解説します。
ヒューマンエラーによる入力ミス
データ入力を行うときに発生するヒューマンエラー(人為的ミス)は、入力ミスの原因の中でも大きな割合を占めています。
たとえば、データ入力作業中の呼び出しによる入力漏れ、体調不良や疲労・ストレスなどによって集中力が途切れてしまい、ミスを招くケースは少なくありません。
また、従業員一人あたりの業務量が多いなど、職場環境が原因によるヒューマンエラーも、原因として考えられます。
データ入力のマニュアルが確立されていない
作業マニュアルがなくデータ入力作業が属人化している場合も入力ミスが起こりやすいです。
データの入力先や参照元の資料・入力手順など、作業内容を細かくマニュアル化していない状態が続いたとき、作業にあたる従業員ごとに異なる入力方法となり、ミスが生じたり入力されたデータの品質に差が出たりします。
入力したデータのチェック体制が整っていない
入力されたデータに不備がないかをチェックする体制や仕組みが構築されていないと、ミスがあっても見逃してしまい、作業品質の低下を招いてしまいます。
システムを活用したチェック体制を用意したり、第三者によるダブルチェックを実施するなど、正確性を維持するための体制や仕組みづくりが大切です。
関連記事:データ入力代行業者とは?料金相場やメリットを徹底解説
ヒューマンエラーによる入力ミスが多い人の特徴
ヒューマンエラーによるミスが多い人には、それぞれ特徴があります。
ヒューマンエラーを起こしやすい人の特徴をご紹介します。
集中力の維持ができない
正確なデータ入力作業を行うためには、集中力を維持する能力が不可欠です。
しかし、黙々と作業を続けることが苦手で集中力が続かない人の場合、作業ミスが生じやすい傾向があります。
また、個々の特性によるもの以外にも、「周囲がうるさく集中できない」「室温や湿度などが適正ではない」など、環境要因によって集中力が持続しないといったケースも少なくありません。
マルチタスクで入力作業を行っている
慢性的な人手不足に陥っている企業では、一人の従業員が複数の業務を兼務しているというケースが珍しくありません。
たとえば、データ入力を行う従業員が、問い合わせの電話応対を兼務しているケースは多いです。
このような場合、入力の途中で電話が入ることでどこまで作業を進めたのかわからなくなり、入力ミスが生じることがあります。
また、本来マルチタスクが苦手な従業員だったというときも、苦手分野を行うことで入力ミスにつながるケースもあります。
データ入力のマニュアルに沿った作業ができていない
作業マニュアルは、どの従業員が作業を行っても同じ品質の作業ができるようにするための重要なツールです。
しかし、従業員によってはマニュアルを見ながら作業を行うことで時間がかかったり、面倒に感じたりすることもあるでしょう。
その結果、最終的にマニュアルを無視した手順で作業をすることになり入力ミスが頻発することもあります。
データ入力のミスを防ぐためのポイント
データ入力のミスを防ぎ、精度の高いものに仕上げるためのポイントをご紹介します。
入力されたデータのダブルチェックを行う
人の手によってデータ入力を行う以上、ミスが生じるリスクは避けて通ることのできない問題といえるでしょう。
リスクを可能な限り減らすためには、ダブルチェックの体制を整えることが大切です。
作業を終えたデータを第三者がチェックすることでミスが発見しやすくなり、作業のやり直しといった余計な時間を抑えることにもつながります。
また、システムやITツールなどを導入できれば、ダブルチェックに必要な人員を他の業務へ充てることができ、会社全体の作業効率化にもつなげることができるでしょう。
データ入力作業をマニュアル化する
作業マニュアルが整備されていない場合には、データ入力作業マニュアルを作成しておきましょう。
作業マニュアルは初めての人でも見たらすぐに作業ができるように、入力手順だけでなく、ダブルチェックの方法など作業が完了されるまでの手順を記載しましょう。
また、作業マニュアルは一度読んで終わりにさせることなく、定期的に読み合わせの機会を設けるなどマニュアル通りの作業を徹底させることが大切です。
関連記事:データ入力を外部委託する際は「精度の高さ」に注目を!
データ入力代行業者への外注も視野に入れる
ダブルチェック体制の構築やデータ入力作業マニュアルの作成・指導などを行ってもデータ入力のミスが頻発する場合には、データ入力代行業者へ外注することも視野に入れてみましょう。
データ入力代行業者はデータ作成のプロのため、依頼することで高い品質を提供してもらうことができるでしょう。
データ入力を外注するメリット
データ入力代行業者へ作業を依頼した場合、入力の精度や品質の向上が期待できます。
また、それまでデータ入力を担当してきた従業員をコア業務に専念させることで、会社全体の業務効率化ができ、コスト削減につなげることもできるでしょう。
データ入力の高い精度だけでなく、企業の業務効率化やコストダウンはデータ入力代行業者を活用する大きなメリットといえます。
データ入力代行業者を探すときの注意点
データ入力代行業者へ作業を依頼する場合、取り扱い製品やサービスに関する情報、顧客情報など機密情報を渡す必要があります。
そのため、万が一情報が漏洩してしまった場合には自社だけでなく顧客にも影響が生じ、最終的には信頼を失墜させるリスクを生じます。
可能な限りリスクを抑えるためには、プライバシーマークを取得していたり大手企業や官公庁との取引があるなど、信頼度の裏付けを明確に提示している業者を選ぶことがなによりも重要です。
また、詳細な見積もりを提示してもらえるかどうかも、業者選びには必要です。
もし見積もりに不明点があり問い合わせても納得のできる回答が得られない場合、請求時に追加料金が上乗せされるなど、トラブルに発展するケースも少なくありません。
信頼できるデータ入力代協業者の場合、Webサイトに過去の案件事例や実績を公開しているケースが多いので、依頼前に入念な確認をすることが大切です。
関連記事:これから依頼される方必見!データ入力代行会社の選び方!
まとめ:データ入力代行ならプロセス・マネジメントにお任せください!
データ入力は一見簡単な作業に見られがちですが、長時間にわたる集中力と正確性が求められる作業です。
一方で、ヒューマンエラーによるミスが起こりやすく、業務に支障が出ることも少なくありません。
データ入力作業のミスが多く、「チェック体制を構築してもなかなか改善ができない」とお悩みの企業担当者様は、プロセス・マネジメントへご相談ください。
プロセス・マネジメントでは、顧客名簿や名刺、手書きの文書など書類で保管されている情報を正確に入力し、データ化するサービスを提供しております。
正確な作業はもちろん、高性能スキャナーを利用したOCRによるデジタルデータへの変換も可能です。
また、当社のスタッフは個人情報保護士の有資格者によって構成され、会社としてもプライバシーマークやDXマークも取得しているため、機密性の高いデータ入力作業も安心してお任せいただける体制を整えております。
正確なデータ入力による業務の効率化を検討されている方は、まずはお気軽にプロセス・マネジメントまでご相談ください。
アンケート結果のまとめ方を解説|自由記述はどうやってまとめる?
新商品や新サービスの開発や顧客満足度調査などのように、さまざまなデータが求められる業務において、アンケート調査は効果的な手段といえます。
しかし、アンケートの量が膨大になると集計作業も煩雑化し、どのようにまとめれば良いのか分からなくなることも多いでしょう。
そこで本記事では、アンケート結果のまとめ方の基本を解説します。
アンケート結果のまとめ方
アンケートは単に多くの回答を得られれば良いというものではなく、それらを集計し正確に分析することで全体の傾向が把握できます。
そのために押さえておきたい基本的な流れが、「集計」「グラフ化」「分析」という3つのプロセスです。
不特定多数の回答者から得たアンケートを一つずつデータとして拾い上げ集計し、それをグラフ化します。
すると、一目で結果が分かるようになるので、可視化されたデータをもとに全体の傾向を分析します。
これにより、アンケートの対象者はどのような考え・意見をもっているのか、何が大きな課題なのか、優先して解決すべき事象や問題などを見つけ出せます。
それは、有効な解決策を立案することにもつながっていきます。
アンケート結果の集計方法
不特定多数の対象者からアンケートの回答を得た後、ひとつ目のプロセスとして「集計」があることをご紹介しました。
一口に集計といってもアンケートの目的や種類によってさまざまな方法があります。今回は代表的な3つの集計方法をご紹介しましょう。
単純集計
単純集計とは、アンケートの設問に応じてどの程度の回答者が答えたか、その実数や割合、平均値などを把握するために用いる集計方法です。
| Q.商品Aを試食した感想をお聞かせください | 回答数(N) | 割合(%) |
| 1.美味しかった | 70 | 70% |
| 2.どちらともいえない | 20 | 20% |
| 3.美味しくなかった | 10 | 10% |
| 計 | 100人 | 100.0% |
上記の例では、全体として7割の回答者が「美味しかった」と回答し、好評を得たという結果が読み取れます。
上記のような設問一つずつのデータをまとめたものを、シングルアンサー(単一回答)形式の単純集計と言います。
複数の質問をまとめて集計するものは、マルチアンサー(複数回答)形式と言います。
クロス集計
クロス集計とは、上記で紹介した単純集計をより詳細にまとめる集計方法です。
単純集計では、回答者や回答数の総数を把握することはできますが、性別や年齢層といった属性までは分かりません。
そのため、どの層に支持されているのか把握することは難しいものです。
単純集計ではまとめられなかった、上記の属性を踏まえて集計する方法をクロス集計とよびます。
| 全体 | 1.美味しかった | 2.どちらともいえない | 3.美味しくなかった | ||
| 全体 | 100 | 70 | 20 | 10 | |
| 性別 | 男性 | 50 | 28 | 15 | 7 |
| 女性 | 50 | 42 | 5 | 3 | |
| 年代 | 男性20代 | 15 | 10 | 3 | 2 |
| 男性30代 | 15 | 8 | 5 | 2 | |
| 男性40代 | 10 | 5 | 3 | 2 | |
| 男性50代 | 10 | 5 | 4 | 1 | |
| 女性20代 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
| 女性30代 | 15 | 11 | 1 | 3 | |
| 女性40代 | 10 | 9 | 1 | 0 | |
| 女性50代 | 10 | 7 | 3 | 0 | |
上記の例では、商品Aは特に女性の若年層に支持される割合が高い一方で、40代以降の男性では意見が割れる傾向が見られることが分かります。
自由記述の集計
自由記述とはその名の通り、複数の選択肢から回答してもらうのではなく、意見や考えを自由に記述してもらった内容をまとめる集計方法です。
単純集計やクロス集計のように機械的にデータを集計できるケースもあれば、アンケートの回答内容を確認し、集計しなければならないこともあります。
自由記述の集計方法について、「自由記述回答のまとめ方」の章でも詳しく解説します。
アンケート結果を可視化するグラフ
集計が終わったら、それらの数値をもとにグラフを作成し可視化します。こちらもデータの種類や特性に応じてさまざまな種類を使い分ける必要があります。
円グラフ
シングルアンサー形式での単純集計結果をグラフ化したい場合には、円グラフが適しています。
一目で回答の割合や傾向が把握でき、見慣れた形式のグラフでもあるため誰にとっても分かりやすい特徴があります。
帯グラフ
帯グラフは帯状の太いラインの中に、それぞれの回答の割合を色分けによって区切って示すグラフです。
円グラフは一目で見やすいメリットがある一方で、複数の設問がある場合にスペースをとってしまい効率的ではありません。
帯グラフであれば、複数の設問に対応したグラフを複数配置でき、限られたスペースを有効活用できます。
棒グラフ
棒グラフとは、回答の選択肢ごとにその数を表したグラフです。
複数の回答が選択できる場合に用いられることが多く、選択肢ごとの高低を一目で確認できることが特徴です。
また、クロス集計の際に、属性ごとの傾向を判断するために用いられることもあります。
折れ線グラフ
折れ線グラフは時系列の変化や年代ごとの比較をするために、縦軸にデータ、横軸に時間軸を設け、それぞれのデータをプロットした後に線で結び表したグラフです。
レーダーチャート
レーダーチャートは中心から外側に放射状に伸びる複数の軸を繋いだ正多角形のグラフです。
たとえば、ある人物のスキルの傾向を集計したり、複数科目のテストの成績を集計したりすることで、長所と短所を分析することもできます。
自由記述回答のまとめ方
自由記述方式のアンケートをまとめる際には、主に数値データを集計する方法と、アフターコーディングとよばれる方法の2種類があります。
たとえば、「1日のランチにかけるお金は平均いくらですか?」という問いに対し、選択肢ではなく自由に金額を記述してもらうとします。
その場合には、そのデータを数値化したうえで平均や中央値、標準偏差、最小値・最大値などを求めます。
また、「ランチで食べたいメニューはありますか?」という問いの場合、数値化することはできないため記載された内容を一覧などにまとめる方法もあります。
アンケート結果のExcelでのまとめ方
アンケートの回答をまとめるために、日々の業務で使用しているExcelを活用できないかと考える方も多いでしょう。
結論からいえば、工夫次第でExcelをアンケート集計に活用することは十分可能です。
一例として、シングルアンサー形式のアンケート結果をまとめる簡単な手順をご紹介しましょう。
- 行(横)にアンケートの設問を入力
- 列(縦)にアンケートの回答選択肢を入力
- 回答者ごとに以下の表に入力していく
| 回答者1 | 設問1 | 設問2 | 設問3 | 設問4 | 設問5 | 設問6 | 設問7 |
| 選択肢A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 選択肢B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 選択肢C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選択肢D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 選択肢E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
上記のように、該当する項目には「1」それ以外は「0」を入力します。
そのうえで、関数のひとつである「COUNTIF」を利用すれば、選択した範囲のセルから「1」の条件にマッチしたセルをカウントすることができます。
すると、アンケート集計の手間が大幅に省けるでしょう。
ただし、簡単なアンケートであれば上記の例に従って集計できますが、複雑な内容になると知識や労力が必要であることから、Excelでの集計には限界があります。
アンケート集計は業者に依頼するのがおすすめ
アンケートの集計作業に関する知識がない、または膨大な量で集計作業に多くの手間を要する場合には、専門業者へ依頼することもひとつの手です。
専門業者へ依頼するメリットや、業者選びのポイントをご紹介しましょう。
業者に依頼するメリット
専門業者はアンケートの集計に関する専門的な知識やスキルに精通しており、正確かつスピーディーにまとめることができます。
また、データの集計やグラフによる可視化によって、そこからどのような傾向が見られるのか精度の高い分析も可能です。
すると、自社の課題や取り組むべき問題の優先度も見えてくるでしょう。
膨大なアンケートを集計する手間がなくなることで、定型業務に割く時間を削減でき、事業企画や製品開発、営業といったコア業務に専念することもできます。
業者選びには注意!
一口に専門業者といってもさまざまな業者が存在し、中には信頼性に乏しく満足な品質が期待できないケースもあります。
特に、他社と比較して価格設定が安すぎる業者や、Webサイトを調べても実績や事例紹介が見つからない業者は要注意といえるでしょう。
また、Webサイトで情報収集を行う際には、そのサービスの運営会社もしっかりと確認しておきましょう。
企業の実態が不明瞭な企業は、たとえば自社で作業を行うことなく海外に拠点を置き、外注先に業務を丸投げしているケースも想定されます。
アンケート集計ならプロセス・マネジメントにお任せ!
信頼できる専門業者をお探しの方は、ぜひ一度プロセス・マネジメントへご相談ください。
プロセス・マネジメントではアンケート回答結果のデータ入力から集計、グラフ化、データ分析までをワンストップで対応しています。
作業を担当するのはすべて日本人スタッフのため、高い集計精度が求められるアンケートも安心してお任せいただけます。
さらに、アンケートの内容によっては、機密情報や営業情報など高度な情報管理が求められるものも多いでしょう。
プロセス・マネジメントは、個人情報保護士資格を保有したスタッフで構成されています。
会社としてもプライバシーマークを取得しているため、万全のセキュリティ体制を整えています。
まとめ
アンケートの結果をまとめるためには、地道な集計作業とグラフによるデータの可視化、さらには高度な分析といったプロセスが必要です。
また、集計方法やグラフにもさまざまな種類があり、アンケートの目的や種類、設問内容などに応じて最適なものを選定しなければなりません。
アンケートの設問数や内容によっては集計方法が複雑化したり、そこから何を読み取れるのか分析も高度化する可能性があります。
そのような場合には、専門業者へ依頼することも検討してみましょう。
信頼性が高く安心して任せられるアンケート集計業者をお探しの方は、プロセス・マネジメントへぜひお気軽にご相談ください。
データ入力代行業者とは?料金相場やメリットを徹底解説
取引先や顧客からいただいた名刺、アンケート調査の回答、経理伝票など、紙に印刷・手書きされた文字をデータとして管理するためには、データ入力作業が必須です。
一見簡単そうに見えるデータ入力ですが、ミスを最小限に抑えスピーディーに作業を遂行するのは意外と難しいものです。
このような面倒な作業を効率化するために役立つ「データ入力代行業者」について、依頼するメリットや料金相場、業者選定のポイントなどを中心に解説します。
データ入力代行サービスでできること
データ入力代行サービスとは、その名の通りさまざまなデータ入力の業務を請け負うサービスのことです。
たとえば、マーケティング部門であればアンケート調査の結果を集計しリストにまとめたり、営業部門であれば自社の顧客情報を一覧にまとめて顧客リストを作ったりと、日々の業務のなかには多くの工数を必要とするものが少なくありません。
そのような定型的な業務を、専門の外部企業へ委託することができるのがデータ入力代行サービスです。
上記以外にも、データ入力代行サービスでは以下のような業務を委託できます。
- 経理伝票の入力・記帳
- 勤怠情報の入力・リスト化
- 請求データの入力
- 支払いデータの入力
- 名刺データの入力
- 手書き文字のデータ化(テキスト入力)
など
データ入力を業者に代行するメリット
データ入力を外部の専門業者へ委託することにより、自社にとってどういったメリットがあるのでしょうか。
社員が他の業務に集中できる
データ入力は量が膨大になるほど多くの手間と時間を要します。
そのため、自社の社員で全てのデータ入力を内製化するとなると、そればかりに人手がとられてしまいマーケティング戦略や営業活動といったコア業務を圧迫することもあるでしょう。
データ入力代行を利用することで定型的な業務の負担を大幅に軽減し、専門性や高度なスキルが求められる業務に集中できます。
コスト削減を狙える
作業に慣れていない自社スタッフがデータ入力を行うと、作業効率は決して高いとはいえず人件費ばかりが膨らんでしまいます。
データ入力代行サービスを担う会社は、多くの企業からの委託を受けておりスピーディーなデータ入力作業を行うことができます。最小限のコストで効率的なデータ集計・入力ができれば、結果としてコスト削減にもつながるでしょう。
ミスのないデータ管理が可能
データ入力代行サービスを担う会社は、スピーディーな作業と同時にミスの少ない正確な作業も行うことができます。
入力ミスが多いと修正や追加など手戻りの作業も増え、業務効率の低下を招いてしまいます。しかし、外部の専門業者へ委託することでそのような懸念もなく、生産性向上が期待できます。
データ入力代行サービスの選び方
データ入力代行サービスを提供する企業は数多く存在し、どこを選べば良いのか迷ってしまうものです。信頼性・品質が高いデータ入力代行サービスを選ぶために、特に注意しておきたい5つのポイントをご紹介しましょう。
1.実績
これまでどういった企業からの依頼を受けてきたのか、案件数や受託企業の実績を確認しましょう。データ入力代行サービスによっては、Webサイトにこれまでの実績を掲載しているところも少なくありません。
また、アンケート集計や顧客リスト作成、経理代行など、受託業務の内容や継続率の高さなどもサービス選定のポイントとなるでしょう。
2.アフターサービス
専門業者とはいえデータ入力を行うのはスタッフである以上、入力ミスを完全になくすことはできません。
重要なのは、ミスや漏れなどが見つかった際に迅速に対応してくれるか、そのような体制が整っているかという点です。
また、業者によっては修正や再依頼の際に追加費用がかかるところもあるため、問題が生じた際のアフターサービスの内容や条件をしっかりと確認しておきましょう。
3.セキュリティ対策
取り扱うデータによっては個人情報や機密情報が含まれる業務も少なくありません。
外部企業に委託するとなると、委託先から大切な情報が漏れるリスクもあることから、セキュリティ対策がしっかりと講じられているかも確認しておきたいところです。
たとえば、データや情報はどのように保管しているか、セキュリティ対策が施された端末を使用しているかなどは最低限チェックしておきましょう。
セキュリティ対策が出来ているかどうか、を確認する際の一つの指針として資格などを取得しているかどうか、も基準となります。プロセス・マネジメントは会社としてもプライバシーマークやDXマークを取得しており情報セキュリティ対策も万全です。
4.急な作業に対応してくれるか
データ入力代行は納期が決められており、ある程度余裕をもって依頼することが基本となります。しかし、ときには業務の締め切りが数日後まで迫っており、短納期で仕上げなければならないこともあるでしょう。
そのような急な作業依頼にも対応できるか、その際の追加料金なども含めて確認しておくと安心です。
5.料金体系
データ入力代行サービスでは、たとえば「住所・氏名の入力が1件あたりそれぞれ◯円」、「シングルアンサー形式のアンケート回答の入力◯円」といったように、料金体系が決められているケースがほとんどです。
委託業者によっても単価は異なるほか、スキャニングやホッチキス外しなどの業務によってオプションが設定されているケースもあります。
データ入力代行業者の料金相場
データ入力代行サービスはどの程度の料金で依頼できるのでしょうか。入力項目に応じた料金相場をご紹介します。
【データ入力基本項目】
- 氏名 2〜4円
- フリガナ 2〜4円
- 性別 1円
- 年齢 1〜2円
- 郵便番号 1〜2円
- 住所 4〜5円
- 生年月日 1〜2円
- 電話番号 2〜3円
- 会社名 2〜4円
- 部署名 2〜3円
- 役職名 2〜3円
- メールアドレス 3〜5円
- URL 3〜4円
【アンケート入力項目】
- シングルアンサー(選択肢から1点を選ぶアンケート) 1円
- マルチアンサー(選択肢から複数を選ぶアンケート) 2〜3円
- フリーアンサー(自由記述式のアンケート) 0.2〜0.5円/文字
たとえば名刺や記名式アンケートなどの場合、「氏名・会社名・住所・電話番号・メールアドレス・URL」など複数の項目を入力しなければなりません。このような場合を想定し、多くのデータ入力代行サービスでは複数の入力項目がセットになったプランも用意しており、たとえば名刺であれば1枚30円から50円程度が相場となっています。
データ入力ならプロセス・マネジメントにご相談ください
品質・信頼性が高いデータ入力代行サービスを探すのは簡単なことではなく、入力ミスや漏れが頻発したり、セキュリティ対策が不十分であることが発覚したりといったケースは少なくありません。
業務改善を請け負っているプロセス・マネジメントでは、経験豊富な日本人スタッフによる正確な入力作業と目視・システムによる二重検査体制を構築しており、99.9%以上という高い入力精度を実現しています。
また、当社には「DXアドバイザー」の資格をもった専門家が在籍しており、ペーパーレス化やDX化に向けたオペレーションの見直しもご提案できます。
セキュリティ面ではプライバシーマークも取得し、万全のセキュリティ体制を構築しているため個人情報や機密情報を取り扱う業務も安心してお任せいただけます。
データ入力作業を委託し業務効率化や生産性向上を図りたいとお考えの企業様は、ぜひプロセス・マネジメントまでご相談ください。
まとめ
データ入力代行サービスの利用はコスト削減や作業ミスを軽減し、企業にとっては生産性向上につながるメリットがあります。
料金体系やアフターサービスの内容、セキュリティ対策なども代行業者によって異なるため、今回紹介した選定ポイントを中心に信頼できる業者を選びましょう。