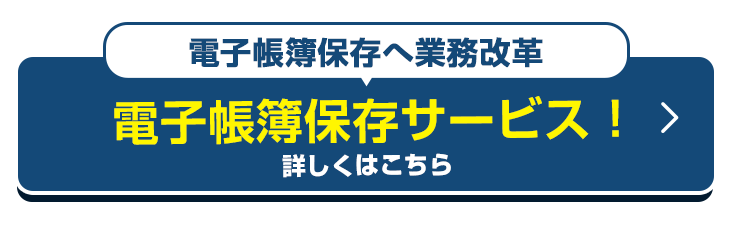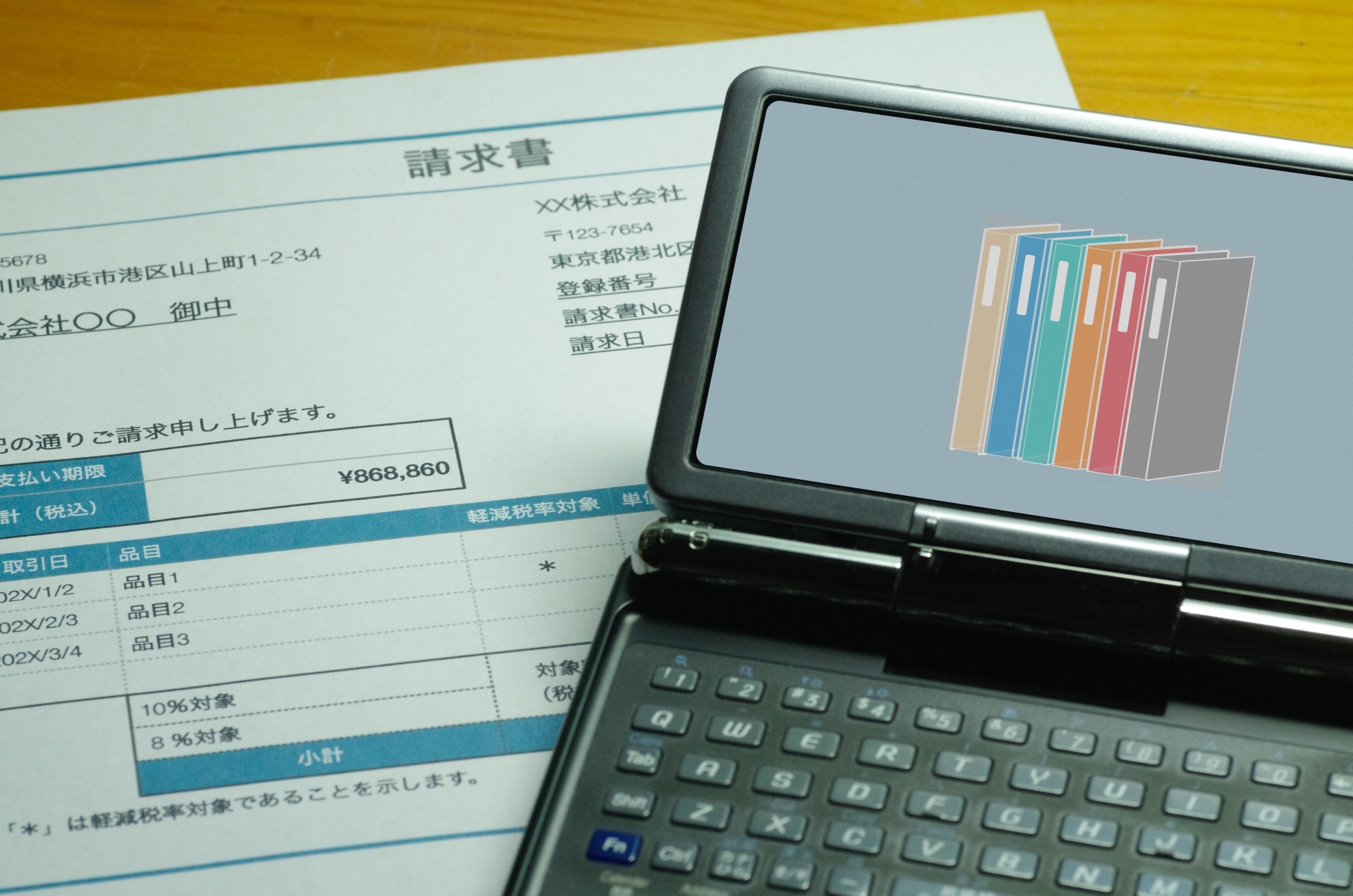電子帳簿保存法における印刷してはいけない理由と対策について
電子帳簿保存法の改正に伴い、2024年1月から電子取引でやりとりされたデータは、電子データでの保存が義務付けられています。
今までは電子データも紙に印刷して保存することができましたが、現在は認められていません。
本記事では、電子帳簿保存法において印刷してはいけない理由とその対策方法について解説します。
紙で保存した際の罰則や例外的に紙で保存できる書類などについても解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
電子帳簿保存法で印刷してはいけないのはなぜ?
電子帳簿保存法で印刷してはいけないのは、以下の3つの理由からです。
- データの真正性確保
- 検索機能の必要性
- 規定の保存要件
それぞれの理由について、以下で見ていきましょう。
データの真正性確保
電子帳簿保存法では、データの真正性、すなわち保存されているデータが後から改ざんされたものではないことを証明する必要があります。
紙の資料では正しいデータが印刷されているのか、改ざんされたデータが印刷されたのかがハッキリしません。
一方、修正・変更履歴が表示されるシステムで管理すれば、データが正しいものであるか改ざんされたものであるかを簡単に判別できるのです。
検索機能の必要性
電子帳簿保存法では、必要な場合に保存しているデータをすぐに取り出せるようにするため、検索機能も必要とされています。
紙の資料で保存していると膨大な量の資料から探さなければいけないため、資料を見つけ出すのに時間がかかります。
一方、日付や取引先名などから資料を検索できる機能を搭載したシステムで管理すれば、時間をかけずに資料を探し出すことが可能です。
規定の保存要件
電子帳簿保存法では、電子データを保存する際の要件が規定されています。
そのため、ただ電子データを保存すれば良いのではなく、規定された保存要件に沿ってデータを保存する必要があるのです。
保存要件の主な内容は、前述した真正性と検索機能の2つです。
真正性と検索機能の詳細なルールを遵守することで、正確で管理しやすいデータ保存が可能になるため、必ず遵守するようにしてください。
関連記事:電子帳簿保存法の対象となる書類について|対象外となるケースとは?
電子帳簿保存法の対象となる書類
電子帳簿保存法の対象となる書類の具体例を紹介します。
対象書類を4つに分類していますので、ぜひ参考にしてみてください。
国税関係帳簿
電子帳簿保存法の対象となる国税関係帳簿には、次のような書類が含まれます。
- 仕訳帳
- 総勘定元帳
- 売掛帳
- 買掛帳
- 現金出納帳
- 固定資産台帳
決算関係書類
電子帳簿保存法の対象となる決算関係書類には、次のような書類が含まれます。
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 試算表
- 棚卸表
取引関係書類
電子帳簿保存法の対象となる取引関係書類には、次のような書類が含まれます。
これらの書類には、相手から受領した書類だけでなく、自己発行の書類の写しも含まれます。
- 請求書
- 見積書
- 納品書
- 注文書
- 領収書
電子取引データ
電子帳簿保存法の対象となる電子取引データには、次のような書類が含まれます。
- 請求書
- 見積書
- 納品書
- 注文書
- 領収書
関連記事:電子帳簿保存法に違反すると罰則がある?導入しない場合はどうなる?
電子帳簿保存法に違反して紙保存した場合の罰則
電子帳簿保存法に違反し、紙で保存した場合の罰則には次のようなものがあります。
- 過少申告加算税
- 重加算税
それぞれの罰則の内容や適用条件について見ていきましょう。
過少申告加算税
「優良な電子帳簿」を作成していれば、過少申告加算税の対象となった場合でも過少申告加算税の税率が5%軽減されます。
過少申告加算税の軽減措置を受けるためには事前の届出が必要なほか、隠蔽・仮装がないことも条件に含まれます。
重加算税
電子帳簿保存法に対する違反のうち、隠蔽・仮装による申告漏れがあった場合、10%の重加算税が課せられます。
隠蔽・仮装とは二重帳簿を作成したり、帳簿を隠したり破棄したりする行為のことです。
【例外】電子帳簿保存法で印刷してもいい書類とは?
例外的に、以下の書類では電子帳簿保存法でも印刷が認められています。
- 自社で電子的に作成した帳簿や書類
- 紙で受け取った書類
- 電子的に作成して紙でやりとりされた書類
これらの書類は紙と電子データの保存を併用できるため、好みの方法での保存が可能です。
それぞれの項目について、以下で見ていきましょう。
自社で電子的に作成した帳簿や書類
自社で電子的に作成した帳簿や書類を自社内で管理する場合、必ずしも電子保存する必要はありません。
具体的には、国税関係帳簿に当たる仕訳帳や総勘定元帳、国税関係書類に当たる貸借対照表や損益計算書などが挙げられます。
紙で受け取った書類
紙で受け取った書類は電子帳簿保存法の適用対象外であるため、紙のまま保存しても問題ありません。
もちろん、紙で受け取った書類もスキャンによる電子保存ができます。
ただし、紙で受け取った書類を電子保存する場合にも電子帳簿保存法における保存要件を満たさなければいけないため、保存要件を満たせない場合は無理に対応する必要はありません。
電子的に作成して紙でやりとりされた書類
自社で電子的に作成して紙でやりとりした書類の控えも、紙のまま保存できます。
紙で受け取った書類と同じく、電子帳簿保存法における保存要件を満たした上で電子保存することも可能です。
関連記事:【電子帳簿保存法をわかりやすく解説】なぜ義務化になるの?|改正点や要件は?
電子帳簿保存法への対応でお困りならプロセス・マネジメントまで
電子帳簿保存法への対応でお困りの方は、プロセス・マネジメントにお問い合わせください。
プロセス・マネジメントでは電子帳簿保存法に対応できるシステムの提供や業務フロー改善の提案などを行っております。
具体的には、現在の運用状況を確認した上で、電子帳簿保存法に対応しやすくなったり業務効率が改善したりするようなアドバイス・提案をしております。
「まだ電子帳簿保存法に対応できていない」というお客様がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。
まとめ
電子帳簿保存法により、2024年1月から電子データでやりとりした書類は電子データでの保存が義務付けられています。
電子帳簿保存法に対応するには、ただ電子化すれば良いだけでなく、電子保存する際の要件を満たしながら保存しなければいけません。
具体的には「データの真正性」「検索機能」という2つの要件が設けられていますので、まだ対応していない方は早めの対応が必要です。
まだ電子帳簿保存法に対応していない方は、プロセス・マネジメントでご対応いたしますので、お気軽にご相談ください。