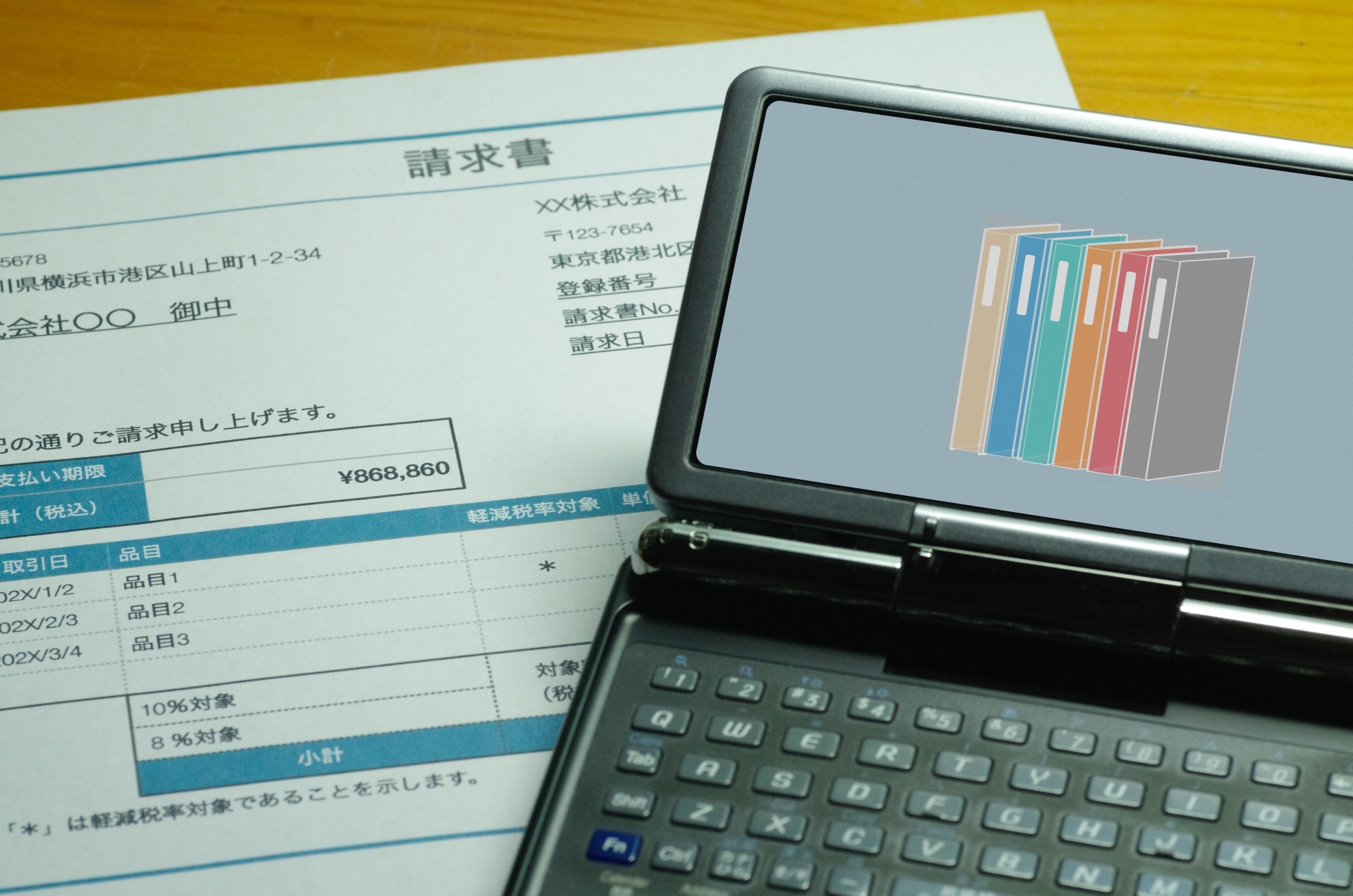電子帳簿保存法の対象となる書類について|対象外となるケースとは?
2022年に改正された電子帳簿保存法。2年間の猶予期間を経て、2024年1月からは特定の条件に当てはまる書類は、すべて電子保存が義務付けられています。
この記事では、電子帳簿保存法の対象となるのはどの書類か、書類が対象外となるケースはどのような場合かについて解説します。電子帳簿保存法への対応を考えている方は、ぜひ最後までお読みください。
目次
1.電子帳簿保存法とは?
電子帳簿保存法とは、法人税や所得税などの国税に関係する帳簿や書類を電子保存する場合の取扱方法などを定めた法律です。
国税に関係する帳簿とは仕訳帳・総勘定元帳などの帳簿を示し、国税に関係する書類とは損益計算書や貸借対照表、請求書、領収書などです。
2022年1月から電子取引のデータは紙に出力して保存することができなくなりました。2年間の猶予があったものの、2024年1月1日からは電子取引のデータはすべて電子データでの保存が義務化されています。
事業規模による取り扱いの変更などもなく、すべての企業と個人事業主が対応しなければなりません。
2.電子帳簿保存法の対象となる書類
電子帳簿保存法の対象となる書類は、次の3つです。
- 電子帳簿保存法に関する対象書類
- 電子取引に関する対象書類
- スキャナ保存に関する対象書類
それぞれの書類について、どのような対応が必要なのかを見ていきましょう。
2‐1.電子帳簿保存法に関する対象書類
電子帳簿保存法に関する対象書類は、大きく分けて、①国税関係書類、②決算関係書類、③自己作成のデータ書類の3つがあります。
それぞれにおける対象書類の具体例は、次の表の通りです。
| 分類 | 対象書類 |
| 国税関係書類 | 仕訳帳売掛帳買掛帳総勘定元帳現金出納帳固定資産台帳売上台帳仕入台帳 |
| 決算関係書類 | 貸借対照表損益計算書棚卸表試算表 |
| 自己作成のデータ書類 | 請求書領収書納品書注文書見積書 |
電子帳簿保存法に関する対象書類の電子保存は任意であるため、電子保存でも紙の保存でもどちらでも問題ありません。
2‐2.電子取引に関する対象書類
電子取引に関する対象書類とは、紙を使用せずオンライン上で作成される取引に関する書類のことを指します。
電子取引に関する対象書類の具体例は、次の通りです。
- 受注書
- 注文書
- 請求書
- 支払い書
- 納品書
- 受領書
- カードの利用明細
- 口座振替の通知メール
取引先から送付された書類も自社から送付した書類も、どちらも電子取引に関する対象書類に該当します。
電子取引に関する対象書類は、紙に出力しての保存ができなくなり、すべて電子保存しなければなりません。
2年間の猶予期間が設けられていましたが、2024年1月1日からはすべての企業と個人事業主で、電子保存が義務付けられています。
2‐3.スキャナ保存に関する対象書類
スキャナ保存に関する対象書類とは、紙媒体でやりとりした取引に関係する書類のことです。スキャナ保存に関する対象書類は、重要度(高・中・低)の3種類に分けられます。
重要度ごとに保存要件が決まっているため、どの重要度に該当するのか、どのように保存すれば良いのかを把握しておくことが重要です。
重要度ごとの書類の具体例は、次の表の通りです。
| 重要度 | 書類の具体例 |
| 重要度(高) | 領収書契約書 |
| 重要度(中) | 請求書納品書約束手形預金通帳預り証借用証書小切手送り状 |
| 重要度(低) | 検収書見積り書注文書 |
なお、スキャナ保存に関する対象書類の電子保存は、電子帳簿保存法に関する対象書類と同じく任意です。
3.電子帳簿保存法の対象外となるケース
ここでは、電子帳簿保存法の対象外となるケースについて解説します。
軽減措置や例外についても解説しますので、参考にしてみてください。
3‐1.対象外となる書類やケース
電子帳簿保存法の対象外となる書類は、手書きで作成された国税に関係する帳簿や国税に関係する書類です。電子帳簿保存法の対象となるのは、初めからすべて電子上で作成された書類であり、手書きで作成したり途中で印刷して手書きに切り替えたりして作成した書類は、対象外になります。
電子帳簿保存法の対象外となった書類は、紙媒体での保存が必要になるため、注意してください。
3‐2.軽減措置や例外について
国税に関係する帳簿のすべてが優良な電子帳簿の要件を満たす場合、過少申告加算税の軽減措置(5%)を受けられます。軽減措置の適用を希望する場合、申請書類と添付書類を税務署に申請する必要があります。
個人事業主が青色申告特別控除を受ける要件を満たす場合も、優良な電子帳簿の要件を満たす必要がある点に注意してください。
4.電子帳簿保存法を導入しないとどうなる?
電子帳簿保存法を導入しないと、罰則を科せられる可能性があります。具体的な罰則の内容は次のとおりです。
- 青色申告の承認取り消し
- 100万円以下の罰金
- 重大な不正であると判断された場合は重加算税が課せられる
青色申告の承認が取り消されると、最大65万円の特別控除が受けられなくなったり赤字繰越ができなくなったりします。
また、電子データを改ざんし、本来納めるべき税金よりも少額の申告や納税をした場合、新たな加算分の課税に加え10%の重加算税が加えられます。
5.電子帳簿保存法の導入ならプロセス・マネジメントまで
電子帳簿保存法の導入ならプロセス・マネジメントにお任せください。プロセス・マネジメントは、バックヤードの業務を効率化する専門集団として、電子帳簿保存法の導入にも取り組んでいます。
個人情報の保護を徹底し、プライバシーマークを取得しているだけでなく、一般社団法人中小企業個人情報セキュリティー推進協会が提供している「DXマーク認証」の第一号でもあるのです。
正確に、効率よく電子帳簿保存法の導入を行うためのノウハウが蓄積されているため、安心してお任せいただけます。ぜひ電子帳簿保存法の導入をする際は、プロセス・マネジメントまでご相談ください。
https://www.pmj.co.jp/denchouhou/
6.【まとめ】電子帳簿保存法の対象となる書類を理解しよう
すべての書類が電子帳簿保存法の対象となるわけではありません。どの書類が電子帳簿保存法の対象となるのか、対象外となるのはどのようなケースかを確認しておきましょう。
曖昧な理解のまま電子帳簿保存法への対応をしてしまうと、本来電子帳簿保存法を導入しなければいけない書類を紙で保存してしまう可能性も考えられます。
ぜひ電子帳簿保存法について理解を深め、適切に導入できるようにしてください。