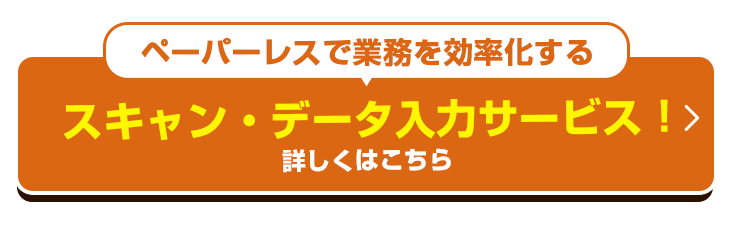紙媒体をデータ化するメリット・方法を徹底解説
書類に印字された顧客リストや手書きの申込書、フォーマットが異なる名刺、領収証など、さまざまな書類を管理している企業も多いのではないでしょうか。
しかし、業務効率化や生産性向上を目指すのであれば、デジタルデータとして保存・管理する必要があります。
本記事では、紙媒体に記録された情報をデータ化することのメリットや、どういった方法があるのかを詳しくご紹介します。
紙媒体をデータ化するメリット

書類として保管・管理しているものをデータ化することで、企業にとってはどのようなメリットがあるのでしょうか。
コストの削減
大量の書類を管理するとなると、インク代やコピー用紙代、さらには書類を管理するための人手も含めて多額のコストが発生します。
しかし、データ化することで書類の印刷コストそのものが削減できるほか、保管にかかるさまざまなコストも大幅に削減できます。
また、重要書類を紛失・破棄した場合の再印刷や再発行の作業や、保存用のファイル、棚なども不要になり、経費節約によって企業全体の利益率向上にもつながるでしょう。
検索性の向上
デジタルデータは特定の情報をスピーディーに探すことができ業務効率化につながります。
従来は膨大な書類の中から目的の情報を手作業で探さなければなりませんでしたが、デジタル化されたデータであればキーワードを検索することで瞬時に必要な情報にアクセスできます。
書類の保管場所を忘れたり、本来とは異なる場所に収納したりといった心配もなく安心です。
情報共有の簡素化
デジタルデータは社内で情報を共有する際にも大いに役立ちます。
書類の場合、たとえば会議の参加者に共有するためにコピーを取ったり、文書を配布・郵送したりする手間がかかりますが、デジタルデータであればメールやチャットにデータを添付するだけで、瞬時に複数の人に共有することができます。
会議の準備が短時間で終えられ、コミュニケーションのスピードも格段に上がることが期待できるでしょう。
業務の効率化
帳簿や領収書など会計に関する書類を整理する際には、書面に記載された数字や内容を会計ソフトに手入力するという手間がかかっていました。
しかし、これらの書類もデータ化できれば、複数のシステムと連携させて自動で処理を進められるため、作業時間の短縮はもちろんのこと手作業での入力ミスも削減できるでしょう。
また、デジタルデータの場合は遠隔地からも容易にアクセスできるためテレワークにも適しています。
保管スペースの削減
大量の書類が溜まっていくと、専用のファイルや棚のほか保管庫などのスペースも必要になります。
特に取引先や顧客の数が多い企業では書類の量も多く、保管スペースを確保するためのコストが無駄になってしまいます。
重要な情報をデータ化することができれば、物理的な書類として保管するものはごく一部に限られ、その他の大部分はクラウドやサーバーに保存することでオフィススペースを有効に活用できるようになります。
環境保護の観点
コンプライアンスの遵守や社会貢献の一環として、環境保護に配慮した事業活動が企業に求められるようになりました。
書類ではなくデジタルデータとして管理することで、紙の生産や輸送、さらには廃棄の際にかかる環境負荷を低減し環境に優しい事業活動を実現できます。
関連記事:データ入力代行業者とは?料金相場やメリットを徹底解説
紙媒体をデータ化する方法

これまで書類をベースに業務を行ってきた企業にとって、紙媒体をデータ化すると聞くとハードルが高く感じられるかもしれません。
紙媒体のデータ化にはさまざまな方法がありますが、今回は自社ですぐにでも実践できる方法をご紹介しましょう。
スキャナで書類を読み取る
オフィスに複合機を設置している企業では、スキャナの機能を活用することでPDFデータに変換することができます。
複合機のスキャナ機能で読み取ったデータは、PCのローカルディスクや社内のサーバー、あるいはクラウドストレージに保存することも可能です。
また、オフィス内に複合機がない企業の場合は、家電量販店などで購入できるスキャナを活用する方法もあります。
スマートフォンアプリで画像からPDFファイルへ変換する
高価な機器やシステムを導入することなく、手軽に書類をデータ化したい場合にはスマートフォンアプリを活用する方法もあります。
領収証やレシートなどをスマートフォンのカメラで撮影し、画像データからPDFファイルへと変換し保存できます。
OCRソフトウェアでテキストを解析
取り込んだPDFファイルから特定の文字列を検索できるようにしたい場合には、OCRソフトウェアでテキストを解析する方法がおすすめです。
スキャナや複合機の中にはOCRソフトウェアが付属しているものも多いですが、多くは当該メーカーのスキャナおよび複合機で取り込んだデータしか解析することができません。
そこで、スマートフォンで撮影した画像や、すでにPDFデータとして保存されているファイルをテキスト解析したい場合には別途OCRソフトウェアが必要です。
コンビニのプリンタを使用する方法
書類の量が極端に少ない、あるいは紙媒体を扱う頻度が少ない場合には、コンビニに設置してある複合機を使用するのもひとつの手です。
大手コンビニチェーンでは1枚あたり数十円程度で書類をスキャンし、そのデータをクラウド上やUSBメモリ、SDカードなどに保存できるサービスを展開しています。
関連記事:電子化が変える書類管理の方法とは?導入するメリットや注意点を紹介|ジェイエスフィット
紙媒体のデータ化で起こり得る問題
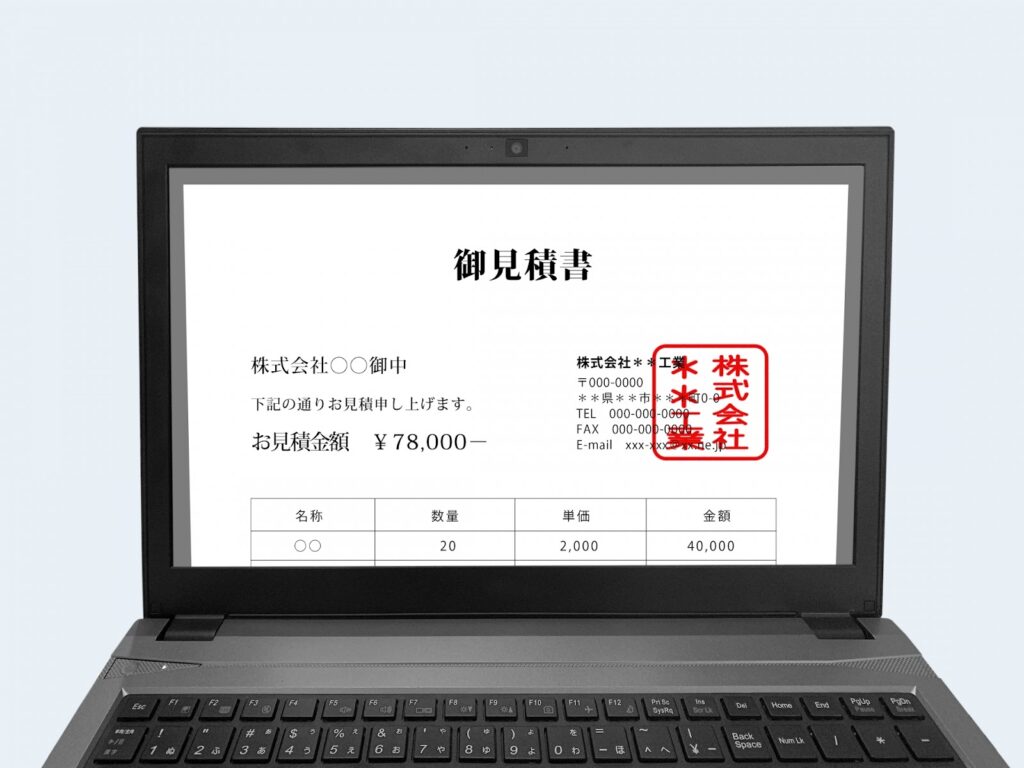
紙媒体のデータ化は複合機やスキャナ、スマートフォンアプリなどがあればすぐにでも始められますが、さまざまな問題やリスクが生じるケースも少なくありません。
解像度の問題
紙媒体をスキャンしてデジタル化する際には、適切な解像度を設定することが重要です。
解像度が低すぎると細かい文字が潰れて読みにくくなったり、図表が不明瞭になったりすることがあります。
反対に、解像度が高すぎるとファイルサイズが大きくなり、ストレージ容量を圧迫したりデータの共有に支障が出ることもあります。
自力で紙媒体のデータ化をする際には、解像度に関する正しい知識や設定のノウハウが必要です。
作業効率と時間
大量の書類をデータ化する際には、多くの時間と労力がかかります。
スキャンの作業はもちろんですが、データ整理や必要な情報のタグ付けなどの作業も必要であり、作業に慣れていないと書類の裏面を取り込んでしまったり、スキャン漏れなどのヒューマンエラーのリスクも増加します。
ファイル管理の複雑さ
紙媒体のデジタル化は単にスキャンすれば良いというものではなく、ファイルを効率的に整理・検索・保管するための工夫も求められます。
特にデータ量が膨大になるとファイル管理も複雑化するため、ファイルの適切な分類や命名規則などを決めたうえで運用を徹底する必要があります。
データ化に関するノウハウがないまま自社でファイル管理を行うと、必要なデータを迅速に見つけることが難しくなる可能性もあるでしょう。
セキュリティの問題
書類をデータ化した場合、不正アクセスによる情報漏えいなどのセキュリティリスクが新たに生じます。
データをサーバーまたはクラウド上で保存している場合や、メールやチャットなどで共有する場合、不正アクセスやデータ漏洩のリスクが高まります。
特に、機密情報や個人情報を含むデータは強固なセキュリティ対策が求められ、暗号化やアクセス制限、定期的なバックアップなどの対策が必要です。
法的要件に触れるリスク
会計書類や税務書類などは法律によって保存期間が定められており、書類をデータ化した場合においても一定期間はデータを残しておく必要があります。
関連する法的要件を理解しないまま運用していると、気付かないうちに法に違反するおそれもあるため専門家の判断や助言を仰ぐことも大切です。
技術的な知識の不足
紙媒体のデータ化においては、複合機やスキャナーといったハードウェアの選定、取り込んだデータを管理するためのデータベースの構築、セキュリティ対策など、技術的な知識が求められます。
自社に十分な技術的知識がないままデータ化を進めてしまうと、エラーなどによって重要なデータが消失する可能性もあるでしょう。
関連記事:データ入力のミスが多い企業必見!トラブルを避けるための対処法
紙媒体のデータ化は専門業者への依頼が安心

上記のような問題やリスクを解消するためには、紙媒体のデータ化を請け負っている専門業者へ依頼するという方法もあります。
専門業者を利用することでどういったメリットがあるのか、企業にとって安心できる理由についてもご紹介します。
短期間で大量のデータ化が可能
大量の書類がある場合には、専門業者に依頼することで短期間に作業を完了できます。
専門業者では高機能のスキャナや自動化されたプロセスによって、大量の書類を迅速に処理できるノウハウを持っています。
自社の社員が1枚ずつ手作業でスキャンする手間が省けるため、1日でも早く書類管理から解放されたい場合には最適な方法といえるでしょう。
高品質なスキャンが可能
専門業者では高品質なスキャニング技術とノウハウを持っており、保存する書類や文字サイズに応じて最適な解像度を設定することができます。
スキャンした後のデータは文字や画像が潰れる心配もなく、クリアで読みやすい状態で情報を保存できます。
コストの最適化につながる
複合機やスキャナ、データベースの構築、OCRソフトの導入など、自社で紙媒体のデータ化をしようとすると多額の設備投資が必要です。
また、それらを運用するための人的コストや、万が一ミスが発生した場合の作業の手戻りなども考慮すると、専門業者へ依頼したほうがトータルのコストを最適化できる可能性があります。
セキュリティ面の担保
専門業者は機密情報や個人情報などの取り扱いにおいて厳重なセキュリティ対策を講じており、不正アクセスやデータ漏えいから保護する体制が整っています。
これにより、情報セキュリティリスクを最小限に抑えることができます。
法的要件の遵守
紙媒体のデータ化に関する法的要件や規制に精通していることも専門業者を利用する大きなメリットといえます。
たとえば、帳簿や請求書、領収証などの会計書類については、電子帳簿保存法に則ってスキャン保存をしなければなりませんが、専門業者の多くは法的要件に沿った対応を行っているため安心して任せられるでしょう。
継続的なサポートを行う場合も
データ化のプロジェクトが完了した後も、継続的なサポートを提供する専門業者は数多く存在します。
例えば、追加のデータ化やデータベースの管理、エラーや障害発生時の対応などが受けられ、これにより企業は安定的な情報管理を継続できます。
紙媒体へのデータ化を依頼する業者の選び方

紙媒体のデータ化を依頼する専門業者を選ぶ際には、以下のポイントを考慮することが重要です。
事例や実績
専門業者の中には、過去に請け負った案件の事例や実績を公開しているところもあります。
自社と同様の業種や類似したプロジェクトを請け負った業者を選ぶことで、データ化にあたって注意しなければならないポイントやリスク対策など有用なアドバイスをもらえる可能性もあります。
セキュリティ規格を取得しているか
データ化を安心して任せられるかを判断するためには、情報セキュリティリスクへの対策が万全であるかを評価する必要があります。
この際、客観的な指標として役立つのがISO/IEC 27001、およびPマークなどのセキュリティ規格です。
これらを取得している専門業者は、第三者機関によって情報セキュリティの安全性や機密性が評価されており安心して依頼できるでしょう。
料金体系
専門業者によっても料金体系や単価は異なります。まずは見積もりを複数の業者から取り、費用対効果を比較検討しましょう。
費用が高い業者が必ずしも良いとは限らず、サービス内容や品質が価格に見合っているかを確認することが大切です。
また、見積書に記載された内訳に不明な内容がないか、透明性があり分かりやすい料金体系であるかも重要なポイントといえます。
対応可能なサービスの範囲
専門業者が提供する作業の内容や範囲を確認することも重要です。
書類のスキャン作業はもちろんですが、データの分類やOCR処理、ファイル形式の変換、クラウドストレージへの保存など、多岐にわたるサービスに対応しているかを確認しましょう。
また、自社のニーズに応じて作業内容のカスタマイズや変更が可能かどうかも大きなポイントといえます。
アフターサポートがあるか
データ化が完了した後のアフターサポートも確認しておきましょう。
追加のデータ化作業はもちろんのこと、サポート窓口の有無や対応時間、トラブル発生時の対応フローなども重要な選定ポイントといえます。
紙媒体のデータ化ならプロセスマネジメントまで
紙媒体のデータ化を安心して依頼できる専門業者をお探しの方は、プロセスマネジメントへご相談ください。
プロセスマネジメントでは、上記でご紹介したような書類のスキャン保存はもちろんのこと、名簿入力や名刺入力といったデータ入力の作業も依頼できます。
通常、これらのデータはOCRソフトによって自動入力できる場合もありますが、文字認識の精度が低くレイアウトが崩れてしまったり、誤った文字として認識されるケースも少なくありません。
特に名刺のような1枚ごとにバラバラのフォーマットの書類はうまく認識できないことも多いです。
そのような場合でもプロセスマネジメントでは正確なデータ入力が可能であり、正確なデータ入力が可能であり、低価格を実現しています。
また、当社のスタッフは個人情報保護士で構成されているほか、会社としてもPマークを取得しているため個人情報や機密情報などのデータ化も安心してお任せいただけます。
まとめ
紙に印字された情報をデジタルデータとして保存・管理するためには、スキャナ保存やスマートフォンアプリでの保存といった方法があります。
しかし、スキャニングの精度や情報セキュリティなどのリスクが立ちはだかり、すぐに移行できない企業も少なくありません。
このような懸念を解消するためには、紙媒体のデータ化を専門に請け負っている業者に相談することもひとつの手といえます。
プロセスマネジメントではスキャナ保存はもちろんのこと、高精度のデータ入力も請け負っています。
デジタル化やDXに向けた第一歩を踏み出したいとお考えの企業様は、ぜひ一度プロセスマネジメントへご相談ください。
スキャン代行で対応できる書類やメリットを紹介|業者を選ぶポイントも解説
ペーパーレス化を実現するために、物理的に保管されている書類や冊子類をスキャニングしデジタルデータとして活用したいと考えている企業も多いのではないでしょうか。
しかし、書類の量が膨大であったり、特殊な書類をスキャニングするためには特別な機器が必要で、自社では対応できないことも少なくありません。
そのような場合に役立つのがスキャン代行サービス。
本記事では、スキャン代行サービスを活用するメリットや取り扱い可能な書類、業者選びのポイントもあわせて紹介します。
スキャン代行サービスとは
スキャン代行サービスとは、その名の通り紙や本をスキャナーで読み取り(スキャニング)、デジタルデータへ変換する作業を代行してくれるサービスのことを指します。
膨大な書類管理に頭を抱えている企業も少なくありません。
そこで、書類整理の手間を削減するためにスキャン代行サービスを活用する企業が増えています。
スキャン代行サービスを使うメリット
スキャン代行サービスを活用することで、企業にとってどういったメリットがあるのでしょうか。
コスト削減と業務効率化
書類をデジタルデータへ変換することにより、PCやデータベース上から目的の書類を素早く検索できるようになります。
また、書類を保管しておくためのスペースや管理者も不要になり、コスト削減につながります。
自社でスキャニング作業を内製化することも可能ですが、作業に慣れていないと多くの時間と人員が必要になり、コストが無駄になってしまいます。
スキャン代行サービスを活用し外部へ作業を委託することで、社員は定型的な作業から解放され、より高度で専門的な業務に専念できるようになるでしょう。
スキャナーの導入が不要
自前でスキャニング作業を行うとなると、大型のスキャナーや複合機を導入しなければなりません。購入費用やリース費用が発生し、メンテナンスコストもかかってしまいます。
しかし、スキャン代行サービスを活用すればスキャナーの導入そのものが不要になり、設置場所の確保やメンテナンスの手間も省くことができます。
書類の劣化を防ぐ
重要書類や書籍などを繰り返し使用していると、シワや破れなどができることもあります。
また、書類の保存状態によっては、インクがかすれて見えにくくなったり、書類そのものが色褪せて劣化してくることもあるでしょう。
スキャン代行サービスでデジタルデータに変換できれば、このような劣化を未然に防ぐこともできます。
関連記事:アンケート結果の効率的なまとめ方|パワポとワードのメリット・デメリットも解説
スキャン代行で対応できる書類の種類
実際にスキャン代行サービスを依頼した場合、どのような書類をデジタルデータに変換できるのでしょうか。
基本的に企業が扱うほとんどの書類はスキャニングに対応できますが、一例をピックアップしてご紹介します。
1.契約書
2.カタログ
3.書籍
4.希少資料
5.ISO文書
6.BCP関連文書
7.紙図面
8.手書き帳票
9.裁判書類
10.通関書類
上記のとおり、契約書や手書き帳票といった1枚単位での紙はもちろんのこと、裁判所類、通関書類といった複数枚の紙がまとまった書類、カタログのような冊子までもスキャニングに対応できます。
関連記事:【電子帳簿保存法をわかりやすく解説】なぜ義務化になるの?|改正点や要件は?
スキャン代行にかかる平均価格
スキャン代行サービスの利用にあたって、特に気になるのがコスト面の問題ではないでしょうか。
スキャン代行サービスの料金は、書類の種類や解像度、モノクロかカラーかによっても変わってきます。
一般的な書類
手書き帳票や資料、BCP関連文書など、一般的な書類の場合は1枚あたり6円から20円程度の料金相場となっています。
| 解像度 | モノクロ | カラー |
| 300dpi | 6円/枚 | 12円/枚 |
| 600dpi | 10円/枚 | 20円/枚 |
契約書・裁判書類・通関書類など
契約書や裁判書類、通関書類などは機密性が高く、高度なセキュリティ対策が求められることから、一般的な書類よりも料金は高額になります。
なお、以下の料金表は1枚ずつ分解してスキャンした場合の金額です。
複数の書類がまとまった状態のまま、1枚ごとに分解せずスキャンするためには手作業が求められるため、上記の金額よりも高額になるケースが一般的です。
| 解像度 | モノクロ | カラー |
| 300dpi | 15円/枚 | 30円/枚 |
| 400dpi | 18円/枚 | 35円/枚 |
カタログ・書籍
カタログや書籍の場合、背表紙から切り離し1枚単位でスキャニング作業を進めることが基本となります。
しかし、希少性の高い本などは切り離すことが難しい場合もあることから、分解しない場合の料金は高額になります。
| 解像度 | 分解する場合 | 分解しない場合 |
| 300dpi | 10円/ページ | 20円/ページ |
| 600dpi | 20円/ページ | 40円/ページこめ |
| ※別途断裁費用 500円/冊 |
図面
図面のような大判サイズの書類は、特殊なスキャナーを使用するためサイズに応じて上記よりも高額な料金相場となっています。
| 解像度 | A1サイズ | A2サイズ | ||
| モノクロ | カラー | モノクロ | カラー | |
| 300dpi | 200円/枚 | 400/枚 | 150円/枚 | 300円/枚 |
| 600dpi | 600円/枚 | 1200/枚 | 300円/枚 | 600円/枚 |
非破壊・袋とじされている書類でもスキャン代行は可能?
本や冊子、図面などの特殊な書類をスキャニングするためには、一般的には1ページずつ切り離したり、スキャナーで読み取れるサイズにカットしたりする作業が必要です。
しかし、希少性の高い書類や、第三者から預かった書類などの場合、物理的に破壊することなくスキャンしたいというニーズもあります。
上記でも紹介した通り、非破壊でのスキャニング作業も可能ですが、通常の料金に比べてコストが高額であるというデメリットもあります。
また、書籍によっては袋とじのページもありますが、綴じた状態のままでは物理的にスキャニングができません。
そのため、袋とじのような特殊な形状の冊子・書籍は、多くのスキャン代行サービスでは非対応となっています。
スキャン代行の業者を選ぶポイント
スキャン代行サービスはさまざまな事業者が提供しており、どのサービスを選べば良いのか分からないという方も多いです。
そこで、業者選びの際に注意しておきたいポイントを紹介しましょう。
対応できる書類の種類やサイズ
ひとつ目のポイントは、スキャニング作業を依頼したい書類の種類やサイズに対応できるかという点です。
資料や一般的な書類などは多くの業者が対応できますが、ポスターや図面といった大判サイズのスキャニングは対応できない業者も少なくありません。
原本の取り扱い
スキャニング作業が終了したあと、多くの場合は原本を返却します。しかし、中にはそのまま破棄・処分してほしいというケースもあるでしょう。
破棄や処分に対応できない業者もあることから、スキャニング後の原本の取り扱いは確認しておきましょう。
納期・費用
急ぎの案件で早急に対応してほしいといったケースもあるでしょう。スキャン代行サービスの納期は1週間前後の場合が多いですが、書類の量が多くなると納期が後ろ倒しになることもあります。
短納期などに個別に対応できるか、納期とコストのバランスがとれているかもあわせて確認しておきましょう。
セキュリティ体制
契約書や裁判書類など、機密情報や個人情報などが記載された書類は厳重な取り扱いが求められます。
十分なセキュリティ体制が確保されていないと、情報漏えいにつながるおそれもあるため、機密文書の取り扱い実績が豊富な業者を選定しましょう。
プロセス・マネジメントはスキャン代行でデジタルデータ化をサポート
スキャン代行サービスを活用したいと考えているものの、信頼できる業者がなかなか見つからない、特殊な書類のスキャニング作業を断られてしまった、などの悩みを抱えている企業も多いのではないでしょうか。
そのような場合には、プロセスマネジメントへご相談ください。一般書類であれば1枚あたり5円からのスキャニングが可能で、契約書や裁判書類といった機密性の高い文書もデータ化が可能です。
万全のセキュリティ体制とリーズナブルな料金、スピーディーな対応でペーパーレス化やDXをサポートいたします。
まとめ
企業が取り扱う書類のなかには、一般書類から機密性の高い情報が記載された契約書、カタログなどの冊子類、大判サイズの図面まで、さまざまなものがあります。
これらのスキャニングには特殊な機器が必要なこともあり、自社で対応できないケースも少なくありません。
ペーパーレス化を実現するためにも、高品質なスキャン代行サービスを活用してみてはいかがでしょうか。
信頼性の高いスキャン代行サービスをお探しの方は、ぜひ一度プロセス・マネジメントへご相談ください。