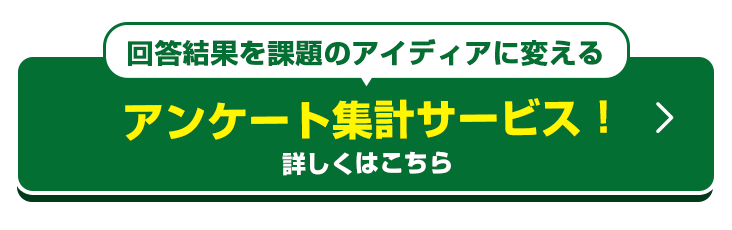高精度なアンケートの設計方法
こんにちは、久保です。
効率的なマーケティング手法の一つとして認知されている
アンケート調査ですが、本当に必要な情報を
入手しようと思うと、なかなか簡単ではありません。
「思ったほど、情報を入手できなかった」
「欲しいデータを得るために
必要なアンケート項目が分からない」
「アンケート調査の正しい進め方を知らない」
など、これまでアンケート調査で困ったことがある方も
多いのではないでしょうか。
アンケート調査には、必ず考えなければならない大前提と
決めなければならない7つの項目が存在します。
確実に効果を実感できるアンケート調査を行うために、
下記のポイントをご確認ください。
セミナーアンケートを有意義なものにする7つのコツを紹介!
こんにちは、久保です。
セミナーと言えば、アンケートは欠かせない存在ですよね。
聴衆の“生の声”を聞けるアンケートは自分では見えていなかった問題点を把握できるため、セミナーの改善や質の向上に非常に有効です。
しかし、アンケートの作り方や集め方がよくないと、参加者が適当に回答してしまい、何の結果も得られず終わる場合もあるでしょう。
せっかくセミナー参加者にご協力いただくのなら、少しでも有意義なアンケートにしたいもの。
そこで、本記事ではセミナーアンケートで押さえるべきコツを7つ紹介します。
セミナーアンケートのよい作り方
ここでは、セミナーアンケートの作り方を手順に沿って確認いていきましょう。
重要項目を前半に設ける
人の集中力には限界があるので、アンケートの後半になるにつれて回答が疎かになりがちです。
そのため、本当に聞きたい項目は前半に設けるようにしましょう。
「どんなアンケート項目が必要がわからない…」という方のために具体例を挙げてみます。
次回からのセミナーを改善するためのアンケートの場合は下記のようにするとよいでしょう。
・開催されたセミナーに対する満足度
・話のわかりやすさや難易度
・セミナーの中で特に参考になった話
・今後実施してほしいセミナーの内容
関連記事:アンケート結果の効率的なまとめ方|パワポとワードのメリット・デメリットも解説
回答しやすい設問にする
アンケートの内容が抽象的だと、回答者は何を書けばよいのかわからなくなってしまい、何の返答も得られなくなるかもしれません。
アンケートの設問を作成する際は、「感想をお聞かせください」といった設問ではなく、
「○○について、どう感じたか教えてください」
「セミナーで一番気に入ったパートと理由は何ですか?」
など、できるだけ具体的に的を絞るように心掛けましょう。
アンケート用紙はA41枚までに収める
セミナーに関してたくさん聞きたいことがあるからと、あれもこれもと項目を詰め込むのは適切だと言えません。
あまりにも項目が多いと回答者が面倒になり、いい加減な回答が増えてしまいます。
有効回答をより多く回収するためにも、アンケート用紙はA4サイズ1枚に収めるようにしましょう。
タイトルには「アンケート」と入れない
参加者の中には、アンケートに対して「ちゃんと回答しなくてもよい」と思っている人もいます。
そのため、
「セミナー振り返りシート」
「ご意見確認シート」
「参加者の皆様の声をお聞かせください」
など、タイトルはアンケート以外の名称にしましょう。
セミナーアンケートの実施・集め方
ここからはアンケート実施の本番におけるポイントを解説します。
休憩時間と回答時間は分ける
セミナーアンケートでよくあるのが、休憩時間と回答時間を兼ねているケースです。
しかし、休憩も兼ねてしまうと回答する時間がなくなり、いい加減なアンケートになってしまうおそれがあります。
そのため、休憩時間と回答時間を分けるようにしましょう。
アンケート用紙は目立つ場所に置く
セミナーで資料やチラシと一緒にアンケートも配る場合、アンケートが資料の中に挟まっていたり、一番下に配置されていたりすると、参加者がアンケートの存在に気付かないおそれがあります。
そういった事態を避けるためにも、アンケート用紙は一番目立つ位置に置くことをおすすめします。
アンケートの回収は講師自ら行う
アンケートを集めるのに、
「席においてお帰りください」
「ボックスに提出してください」
といった方法では、適当に回答したり提出せずに帰ったりする人が増えてしまいます。
有効なアンケートをより多く集めるには、セミナー講師自ら回収を行うのが効果的です。
アンケートの入力・集計はプロセス・マネジメントにお任せ!
セミナーアンケートの作り方・集め方のコツはご理解いただけましたでしょうか?
アンケートを実施したら、次はその結果の入力・集計です。
とはいえ、大量にあるアンケートを自分で入力するのは一苦労…。
集計作業にも多大な時間と手間がかかります。
「大量にあるアンケート結果を入力する時間がない…」
「集計結果を手っ取り早くデータ化したい…」
とお考えなら、データ入力精度99.9%を誇る弊社にご依頼ください!
もちろん、セキュリティ体制も万全なため、セミナー参加者の個人情報が漏えいする心配はいりません。
セミナーアンケートのことなら、お気軽にご相談ください。
効果的なWebアンケートを実施するためには?
こんにちは、久保です。
今回は、Webアンケートを実施する際のポイントをご紹介します。
はがきや封書といった紙媒体の場合、アンケートの到着や
集計に時間がかかるため、次のアクションまでに間が空き、
顧客とのつながりが途切れてしまう可能性があります。
一方、Webの場合は瞬時に回答が届くため、
アンケートの結果をすぐに活用することが可能です。
また、集計して顧客が閲覧できるようサイト上に公開するなど、
双方向的なコミュニケーションツールとしても利用できます。
ただし、紙媒体と比べ回答率が低いとされるWebでは
ポイントを押さえてアンケートを作成しなければ、
充分なデータを得ることはできません。
これからご紹介する点に留意しながら、
効果的なWebアンケートを作成・実施して、
マーケティングに活用していきましょう。
(さらに…)
アンケート調査の種類はさまざま!どう選べばよい?
こんにちは、森田です。
突然ですが、皆様は「アンケート」と聞いて、
どのような調査方法を思い浮かべますか?
雑誌でよく目にするハガキでの読者アンケートをはじめ、
セミナー会場で行われる講演後のアンケート調査、
電話での世論調査など、その種類はさまざまです。
最近では、インターネットを用いた調査も増えてきましたが、
ハガキや調査票、電話・FAXによるアンケートもまだまだ多く、
「どの方法でアンケートを実施しようか…」と
お悩みのご担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、アンケート調査を「定量調査」と「定性調査」に分け、
それぞれどのような方法があるのかをご紹介いたします。
(さらに…)
アンケート調査やテレアポで役立つ、有用な顧客リストの作り方。
こんにちは、森田です。
早いもので当ブログも年内更新は残り2回となりました。
今回は、質の高いアンケート調査やテレアポを行うための
顧客リストの作り方をお伝えいたします。
新年早々スタートダッシュが切れるように、
ぜひ良質な顧客リストを作っておきましょう。
アンケート結果を分かりやすく伝えるための報告書の書き方
こんにちは、森田です。
これまで当ブログの中で、アンケート集計・アンケート入力に関する記事をご紹介してまいりましたが、本記事では「調査報告書」を作成する際に気をつけるべきことをご紹介いたします。
関連記事:アンケート結果の効率的なまとめ方|パワポとワードのメリット・デメリットも解説
タイトルの付け方には工夫を
「タイトル」は、調査報告書を見た際に最初に目に入る場所です。
例えば、官公庁で用いられるものや社内報告書などの場合は、オーソドックスなタイトルが無難でしょう。
しかし、ニュースリリースやプレスリリースのように多くの人が目にする対外的な報告書になると、タイトルに求められる要素も変わってきます。
アンケート結果の報告書を多くの人に向けて発信する場合は、数字を用いて興味を引くものや、タイトルを読んだだけで調査内容・結果を想像できるようなものが良いでしょう。
アンケートの趣旨は分かりやすく
アンケート結果の報告書において、冒頭でアンケート調査の趣旨や目的を明記しておくことも必要です。
パッと見ただけで、「何についてのアンケートなのか」「どういった意図で行ったアンケートなのか」が分かる報告書であれば、内容を読んでもらえる可能性は大きく向上します。
調査対象も必ず明記しましょう
調査対象は、アンケートの精度を決定付ける要素と言っても過言ではありません。
アンケート結果の報告書には年齢や性別、居住エリアといった調査対象の属性と人数は忘れずに明記しましょう。
調査期間・日数の書き忘れに注意
つい忘れてしまいそうになりますが、調査期間や実施日数も重要な情報の一つです。
同じ調査でも、季節や日数によって、アンケート調査の持つ意味合いが変わってきます。
期間や日数は必ず明記しましょう!
信頼性に関わる調査・回収方法
「調査方法や回収方法が記載されているか否か」実はこれが、アンケートの信頼性に大きく関わることをご存知でしょうか?
街頭調査なのかWEB調査なのか、調査方法によってアンケートの質は変わってきます。
また、回収方法の記載の有無によって、どういった経緯で入手したデータなのかといったデータの信頼性にも大きな影響を及ぼします。
回収状況も正確に記載しましょう
アンケートの回収数や有効回答数といった回収状況も、正確に記載しましょう。
例えば回収数が100件であっても、100件中100件なのか、1,000件中100件なのかによって、¥100件という数字の持つ意味も変わってきます。
客観的にデータを比較するためにも、回収状況は重要な数字です。
アンケート結果はきちんと要約を
調査報告書を提示する際、もちろん前述の6つの要素だけでも問題はありませんが、そこにデータを基にした報告者の考察が含まれていると、その報告書の質はさらに向上します。
「このデータで、どのようなことが分かったのか」
「どのように活用できるのか」
を考えやすくなりますので、ぜひアンケート調査の結果を要約、追記しておきましょう。
アンケート結果の入力・集計はプロセス・マネジメントにお任せ!
アンケートは、「調査をしたら終わり」ではありません。そこで得られた結果をしっかりと報告書にまとめるまでが、アンケート調査なのです。
「アンケートを実施したけれど、集計する時間がない…」
「膨大なアンケート結果を入力するのは面倒…」
という方は、ぜひ弊社にアンケート入力・集計をご依頼ください。
弊社のデータ入力精度は99%以上と極めて高いため、集計した結果から抽出されたデータは、そのまま調査報告書にご活用いただけます。
アンケート入力・集計に関することは、ぜひ弊社にお任せください。
これから依頼される方必見!データ入力代行会社の選び方!
こんにちは、久保です。
手間やコストの削減といった業務効率化に加え、入力精度の
高さなどから、多くの企業様が利用しているデータ入力代行。
IT化の進む情報化社会の日本において、データの入力・管理は
非常に重要な業務となっております。
今回のブログでは、これからデータ入力代行を依頼しようと
お考えの皆様に、データ入力代行会社の大まかな特徴と
選び方のコツをご紹介いたします。
ぜひ今後ご依頼になる際のご参考までにご覧ください。
各種データ入力・集計業務のご紹介
こんにちは、森田です。
これまで当ブログの中で、データ入力のメリットをご紹介して
まいりましたが、ここで改めまして、弊社が行っているデータ入力
業務のご紹介をさせていただきます。
弊社がお請けするデータ入力業務は、主に以下の5種類です。
・アンケート入力・集計
・名簿入力
・名刺入力
・応募ハガキ入力
・テキスト入力
どの業務も御社自ら行おうと思うと、手間や時間がかかってしまう
ものばかりです。下記では各種データ入力業務の説明をさせて
いただきます。
アンケート調査では5段階評価での設問作成がおすすめ
こんにちは、鈴木です。
皆様はこれまでアンケート調査を行った際、「思ったようなデータを得られなかった…」という経験はありませんか?
「回答数は問題ないのにデータの質が悪い」という場合、もしかすると“アンケート調査の聞き方”に問題があるかもしれません。
弊社では質の高いデータを入手するアンケート方法として、5段階評価による設問作成をおすすめしております。
関連記事:アンケート結果の効率的なまとめ方|パワポとワードのメリット・デメリットも解説
アンケート調査を5段階評価にする意義
5段階評価にする意義としては、主に3つ挙げられます。
ニュートラルな意見を拾える
アンケート調査における5段階評価の項目としては、「かなり良い・良い・どちらとも言えない・悪い・かなり悪い」などが挙げられますが、中でも「どちらとも言えない」という選択肢は、5段階評価を用いる一番の利点ともいえます。
日本人は無難な答えを選びがちなため、「困ったら普通を」と考えがちです。5段階評価のアンケート調査では、こうした「普通の答え」を得られることに意味があります。
質問によっては、「はい」「いいえ」に分けることが難しい場合もあるため、こうしたニュートラルな回答は非常に効果的なのです。
直感的に選ぶことができる
弊社にご相談いただく内容の中に、「詳細に知りたくて7段階評価にしたけど、効果がいまいち」というものがあります。
確かに5段階評価で詳細なデータが得られるのであれば、7段階評価にすればもっと詳細なデータを入手できると思われがちですが、そうとも限りません。
例えば、同じ“良い”という評価でも、「非常に良い」「かなり良い」「良い」と3段階あった場合、自分の思う“良い”は、「非常に」なのか「かなり」なのかで回答者が悩んでしまう可能性もあるでしょう。
その点「かなり良い」「良い」だけであれば、直感的にすぐ回答を決めることができます。アンケート調査では、スピード感も大切なポイントです。
あまり時間をかけず、スピーディに答えられるような設問設定・項目設定が望ましいでしょう。
多様な質問に利用できる
前述の通り、5段階評価のメリットの一つに“多様な質問に対応できる”点が挙げられます。
例えば、「Aという商品が好きですか?」という質問に対し、「はい」「いいえ」だけの2択式では、どちらでもない人の意見を拾うことができず、自由記述式だった場合、一人ひとり異なる回答をカテゴライズするのは困難です。
その点、5つの内から当てはまる選択肢を選べる5段階評価なら、「好きでも嫌いでもない人」の意見を拾え、さらにカテゴライズも簡単です。
感情を量る質問や答えにくい内容の質問などにも活用することで、質の高いデータを入手できます。
5段階評価でアンケートを作る際のポイント
これまでご紹介したように、5段階評価は非常に質の高い回答を得ることのできる調査方法ですが、気をつけなければいけない点もあります。
質問の内容は明確にしましょう
いくら詳細なデータを入手できる5段階評価であっても、質問の意図が不明瞭だと、正確に答えることができません。
質問を作る際には、誰もが答えやすい内容にしましょう。
また、質問が不明確な場合の「どちらとも言えない」という回答は、他に選べる項目がないゆえの“消極的な選択”にすぎませんが、質問が明確な場合の「どちらとも言えない」は、質問を理解した上での“積極的な選択”になります。
このように意味のあるアンケート調査にするために大切なのは、アンケート調査の目的をしっかりと定め、明確で答えやすい質問内容を考えることが大切です。
アンケート集計と入力はプロセス・マネジメントにお任せください
しっかりと質問内容を考え、満足のいくアンケート調査を行えたら、最後にアンケートの集計と入力をしなければいけません。
膨大な数の回答を正確に集計し、ミスなく入力しようと思うと手間も時間もかかってしまいます。
万が一集計結果や入力内容に誤りがあれば、せっかくアンケート調査で得たデータを有効活用できません。
もしもアンケート調査の集計や入力でお困りの際は、顧客満足度90%を誇る弊社にお任せください。
アンケート集計を行う際には、 最適な集計方法の選択が重要です。
こんにちは、森田です。
現在、世の中には多種多様なアンケートがあります。
商品やサービスの満足度を計るものから、
考え方や暮らし方の傾向を調べるものまで、
企業や店舗だけでなく、公的機関や自治体も行っています。
しかし、アンケートなどでデータ集計を行う際には、
気をつけなければいけないことがあります。
それは、集計の種類を知った上で項目設計を
行う必要があるという点です。
今回のブログでは、最適な項目設計を行い、
有益なアンケート集計とするためのコツをご紹介いたします。
(さらに…)