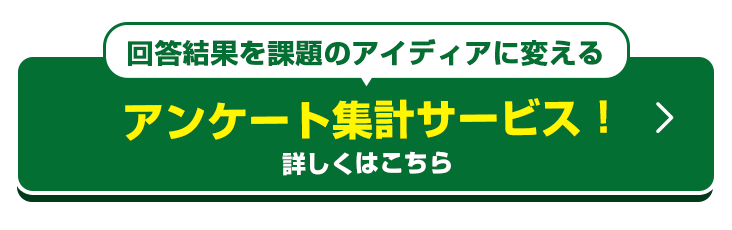アンケート結果を分かりやすく伝えるための報告書の書き方
こんにちは、森田です。
これまで当ブログの中で、アンケート集計・アンケート入力に関する記事をご紹介してまいりましたが、本記事では「調査報告書」を作成する際に気をつけるべきことをご紹介いたします。
関連記事:アンケート結果の効率的なまとめ方|パワポとワードのメリット・デメリットも解説
タイトルの付け方には工夫を
「タイトル」は、調査報告書を見た際に最初に目に入る場所です。
例えば、官公庁で用いられるものや社内報告書などの場合は、オーソドックスなタイトルが無難でしょう。
しかし、ニュースリリースやプレスリリースのように多くの人が目にする対外的な報告書になると、タイトルに求められる要素も変わってきます。
アンケート結果の報告書を多くの人に向けて発信する場合は、数字を用いて興味を引くものや、タイトルを読んだだけで調査内容・結果を想像できるようなものが良いでしょう。
アンケートの趣旨は分かりやすく
アンケート結果の報告書において、冒頭でアンケート調査の趣旨や目的を明記しておくことも必要です。
パッと見ただけで、「何についてのアンケートなのか」「どういった意図で行ったアンケートなのか」が分かる報告書であれば、内容を読んでもらえる可能性は大きく向上します。
調査対象も必ず明記しましょう
調査対象は、アンケートの精度を決定付ける要素と言っても過言ではありません。
アンケート結果の報告書には年齢や性別、居住エリアといった調査対象の属性と人数は忘れずに明記しましょう。
調査期間・日数の書き忘れに注意
つい忘れてしまいそうになりますが、調査期間や実施日数も重要な情報の一つです。
同じ調査でも、季節や日数によって、アンケート調査の持つ意味合いが変わってきます。
期間や日数は必ず明記しましょう!
信頼性に関わる調査・回収方法
「調査方法や回収方法が記載されているか否か」実はこれが、アンケートの信頼性に大きく関わることをご存知でしょうか?
街頭調査なのかWEB調査なのか、調査方法によってアンケートの質は変わってきます。
また、回収方法の記載の有無によって、どういった経緯で入手したデータなのかといったデータの信頼性にも大きな影響を及ぼします。
回収状況も正確に記載しましょう
アンケートの回収数や有効回答数といった回収状況も、正確に記載しましょう。
例えば回収数が100件であっても、100件中100件なのか、1,000件中100件なのかによって、¥100件という数字の持つ意味も変わってきます。
客観的にデータを比較するためにも、回収状況は重要な数字です。
アンケート結果はきちんと要約を
調査報告書を提示する際、もちろん前述の6つの要素だけでも問題はありませんが、そこにデータを基にした報告者の考察が含まれていると、その報告書の質はさらに向上します。
「このデータで、どのようなことが分かったのか」
「どのように活用できるのか」
を考えやすくなりますので、ぜひアンケート調査の結果を要約、追記しておきましょう。
アンケート結果の入力・集計はプロセス・マネジメントにお任せ!
アンケートは、「調査をしたら終わり」ではありません。そこで得られた結果をしっかりと報告書にまとめるまでが、アンケート調査なのです。
「アンケートを実施したけれど、集計する時間がない…」
「膨大なアンケート結果を入力するのは面倒…」
という方は、ぜひ弊社にアンケート入力・集計をご依頼ください。
弊社のデータ入力精度は99%以上と極めて高いため、集計した結果から抽出されたデータは、そのまま調査報告書にご活用いただけます。
アンケート入力・集計に関することは、ぜひ弊社にお任せください。
アンケート調査では5段階評価での設問作成がおすすめ
こんにちは、鈴木です。
皆様はこれまでアンケート調査を行った際、「思ったようなデータを得られなかった…」という経験はありませんか?
「回答数は問題ないのにデータの質が悪い」という場合、もしかすると“アンケート調査の聞き方”に問題があるかもしれません。
弊社では質の高いデータを入手するアンケート方法として、5段階評価による設問作成をおすすめしております。
関連記事:アンケート結果の効率的なまとめ方|パワポとワードのメリット・デメリットも解説
アンケート調査を5段階評価にする意義
5段階評価にする意義としては、主に3つ挙げられます。
ニュートラルな意見を拾える
アンケート調査における5段階評価の項目としては、「かなり良い・良い・どちらとも言えない・悪い・かなり悪い」などが挙げられますが、中でも「どちらとも言えない」という選択肢は、5段階評価を用いる一番の利点ともいえます。
日本人は無難な答えを選びがちなため、「困ったら普通を」と考えがちです。5段階評価のアンケート調査では、こうした「普通の答え」を得られることに意味があります。
質問によっては、「はい」「いいえ」に分けることが難しい場合もあるため、こうしたニュートラルな回答は非常に効果的なのです。
直感的に選ぶことができる
弊社にご相談いただく内容の中に、「詳細に知りたくて7段階評価にしたけど、効果がいまいち」というものがあります。
確かに5段階評価で詳細なデータが得られるのであれば、7段階評価にすればもっと詳細なデータを入手できると思われがちですが、そうとも限りません。
例えば、同じ“良い”という評価でも、「非常に良い」「かなり良い」「良い」と3段階あった場合、自分の思う“良い”は、「非常に」なのか「かなり」なのかで回答者が悩んでしまう可能性もあるでしょう。
その点「かなり良い」「良い」だけであれば、直感的にすぐ回答を決めることができます。アンケート調査では、スピード感も大切なポイントです。
あまり時間をかけず、スピーディに答えられるような設問設定・項目設定が望ましいでしょう。
多様な質問に利用できる
前述の通り、5段階評価のメリットの一つに“多様な質問に対応できる”点が挙げられます。
例えば、「Aという商品が好きですか?」という質問に対し、「はい」「いいえ」だけの2択式では、どちらでもない人の意見を拾うことができず、自由記述式だった場合、一人ひとり異なる回答をカテゴライズするのは困難です。
その点、5つの内から当てはまる選択肢を選べる5段階評価なら、「好きでも嫌いでもない人」の意見を拾え、さらにカテゴライズも簡単です。
感情を量る質問や答えにくい内容の質問などにも活用することで、質の高いデータを入手できます。
5段階評価でアンケートを作る際のポイント
これまでご紹介したように、5段階評価は非常に質の高い回答を得ることのできる調査方法ですが、気をつけなければいけない点もあります。
質問の内容は明確にしましょう
いくら詳細なデータを入手できる5段階評価であっても、質問の意図が不明瞭だと、正確に答えることができません。
質問を作る際には、誰もが答えやすい内容にしましょう。
また、質問が不明確な場合の「どちらとも言えない」という回答は、他に選べる項目がないゆえの“消極的な選択”にすぎませんが、質問が明確な場合の「どちらとも言えない」は、質問を理解した上での“積極的な選択”になります。
このように意味のあるアンケート調査にするために大切なのは、アンケート調査の目的をしっかりと定め、明確で答えやすい質問内容を考えることが大切です。
アンケート集計と入力はプロセス・マネジメントにお任せください
しっかりと質問内容を考え、満足のいくアンケート調査を行えたら、最後にアンケートの集計と入力をしなければいけません。
膨大な数の回答を正確に集計し、ミスなく入力しようと思うと手間も時間もかかってしまいます。
万が一集計結果や入力内容に誤りがあれば、せっかくアンケート調査で得たデータを有効活用できません。
もしもアンケート調査の集計や入力でお困りの際は、顧客満足度90%を誇る弊社にお任せください。
アンケートの回答率を上げるための秘訣とは?
こんにちは、久保です。
商品やサービスの満足度をはじめ、
市場の動向、ニーズの変化を把握する手段として、
多くの企業・店舗が行っているアンケート調査ですが、
「なかなか思ったように回答率が上がらない」などと
お悩みのご担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか?
また、仮に回答が多く集まったとしても、
「その他」の選択肢を選ぶ人や、
自由記入欄に何も書いてくれない人が多いと、
その集計結果から具体的な内容が把握できず、
せっかくの調査が無駄に終わってしまう可能性があります。
「毎回、アンケートの回答率が低い」
「アンケートを集計しても、いまいち傾向がつかめない」
といった場合、もしかしたら…
アンケートの設問に問題があるのかもしれません。
ここでは、アンケートの成果でお悩みのご担当者様に向けて、
「回答率が上がる設問の作り方」をご紹介いたします。
会社説明会のアンケートで、聞いておくべきポイントは?
こんにちは、木村です。
新卒採用にあたって、学生たちに御社の事業をPRする
「会社説明会」は欠かせません。
しかし、新卒の採用活動を始めたばかりの担当者様の中には、
「どんな内容がいいのか」とお悩みの方もいらっしゃるでしょう。
また、毎年のように新卒採用を行っている企業でも、
「最近の学生はどんなことを知りたいのか」
「どういった仕事に興味を持っているのか」などについて、
その傾向を把握するのは難しいものです。
こうした悩みを抱えている担当者様にオススメなのが、
会社説明会の後にアンケートを実施することです。
毎回、説明会の後にアンケートを行えば、
前回のアンケート結果を踏まえて、
「次回の説明会の内容を少し変更してみる」
「採用ホームページの見せ方を変えてみる」
などと、根拠に基づいた採用活動ができるようになります。
また、学生から寄せられる多くの感想や意見は、
来年以降の採用活動にも生かせることでしょう。
では、会社説明会の後に行うアンケートで
具体的にどのようなことを聞けばいいのでしょうか?
今回は、そのポイントをご紹介いたします。
スキャニングで電子化した文書をシステムで管理するには?
こんにちは、木村です。
現在、調査票やアンケート用紙、注文書、契約書、
商品企画書、建築図面、社内報などをスキャニングし、
データとして管理する企業が増えてきました。
こうした文書の電子化には、
オフィスの省スペース化につながる、
紙代・印刷代を削減できるなど、
さまざまなメリットがありますが、
その中でも大きいのが
あらゆるデータをシステマチックに管理できること。
システム上で電子データを保存し、適切に管理することで、
業務効率やセキュリティレベルをさらに高めることができます。
ここでポイントとなるのは、
システム導入時に適切なフローを踏むこと。
今回は、スキャニングで文書を電子化した後、
そのデータをシステムで適切に管理していくために
必要なフローをご紹介いたします。
医療機関におけるアンケート項目作成のポイント
こんにちは、木村です。
「アンケート」と一口に言っても、
新商品を開発するためのマーケティング調査や
サービスに対する顧客満足度調査など、
実に様々な種類が存在します。
これまでもアンケート調査のポイントをお伝えしてきましたが、
今回は病院やクリニックといった医療機関における
患者満足度調査を行う際のポイントを解説いたします。
特に医療機関での患者満足度調査の場合、
従来のマーケティング調査や顧客満足度とは異なるため、
アンケート項目の設定には工夫が必要です。
漠然と設定したアンケート項目に答えてもらうだけでは、
有意義な患者満足度調査になるとは言えません。
最適なアンケートの作成方法(取り方)とは?
こんにちは、久保です。
現在、新商品の企画・開発、新規事業の立案、
出店エリアの選定など、さまざまな目的で
アンケートが行われている一方、
「最適なアンケートの作成方法」や
「アンケートの取り方のコツ」については、
社内でうまく共有されていないケースも少なくありません。
特に、初めてアンケートを作成する際、
「どうやって質問を考えればいいの?」と
お悩みの担当者も多いのではないでしょうか。
今回は、アンケート作成で悩まれている担当者に向けて、
質問文を考えるコツなどをご紹介いたします。
「アンケート」って何語?アンケートの取り方をプロの視点から解説!
こんにちは、木村です。
藪から棒ですが、雑学クイズをひとつ。
Q:私たちがよく耳にする「アンケート」は何語でしょうか?
A:正解は「フランス語」。
アンケートはフランス語で「調査」という意味です。
質問項目が記載された調査票を用いて、複数の人に同じ質問をしてデータ収集を行います。
比較的簡単で便利な手法なので、企業のマーケティングや学術的な調査など、さまざまなアンケートが実施されています。
アンケート調査を行うにあたっては、正確なデータを効率よく集めたいものです。
質の高いデータが集まらなければ、せっかくの調査結果を十分に活かすことができません。
本記事ではアンケート調査の精度を上げ、より正しいデータを確実に取得する方法について解説します。
アンケートの取り方のポイント
アンケート調査で正確なデータを得るには、事前に絞り込んだアンケートの目的とターゲットに沿って、きちんと熟考された調査票の作成が大切です。
重要なポイントは以下の3つです。
1.曖昧さを避ける
2.誘導の回避
3.取りこぼしのフォロー
曖昧さを避ける
質問文がどちらとも取れるような曖昧な言い回しだと、そこでつまずいて回答意欲が損なわれたり、あるいは適当に答えたりして正しいデータが得られなくなってしまいます。
たとえば、「あなたは趣味にどのくらいかけますか」というような質問は、「どのくらい」が「時間」なのか「金額」なのか不明です。
回答者が途中で悩まず、どんどん回答していけるように質問文は誤解を生むような曖昧な言い方は避け、誰にでもわかりやすい平易な表現を用いましょう。
誘導の回避
また、一定方向へ誘導するような言い回しがあると、回答者に誤ったイメージを与えたり、バイアスがかかったりしてしまい、正しいデータが得られなくなってしまいます。
たとえば、「○○という商品はどのように役に立ちましたか」という質問は、「○○が役に立つ商品である」という前提に立って回答を一定方向へ誘導していることになります。
幅広く意見を収集することで実態に即した、より正しいデータが得られます。
・回答者の選択肢を限定するような質問になっていないか
・主観を含まない、中立・公正な表現になっているか
常に留意する必要があります。
取りこぼしのフォロー
「AかBか」で単純に答えられるものはそう多くありません。
「AでもBでもない」「その他」といった回答のなかには、さまざまな意見が一緒くたになって埋もれています。
それを取りこぼさず丁寧に抽出できるよう、回答の選択肢はあらゆる可能性を考慮した適度に細分化されたものが望ましいといえます。
あるいは「その他」の項目を選択した場合は、自由記述式で具体的に回答してもらうのも一つの手です。
ただし、「その他」「どちらでもない」といった回答が、あまりにも多くなりすぎると、そのデータは意味を成さなくなってしまいます。
関連記事:アンケート結果の効率的なまとめ方|パワポとワードのメリット・デメリットも解説
◆アンケートの集計はプロにおまかせ◆
以上のポイントを押さえ正確なデータを収集したら、それを生かすために集計・分析に取りかかります。
できるだけ迅速に行いたいところですが、日々の業務の合間に膨大なデータ処理を行うことは実際問題なかなか難しいことでしょう。
そういう場合は、アンケート実施後の作業をプロに委ねるのも一つの方法です。
弊社では、アンケートのデータ入力および集計業務を承っております。
明快でリーズナブルな料金体系に加え、入力精度99%という高品質を誇り、顧客満足度90%という高い信頼をいただいております。
もちろん、セキュリティ対策も万全です。
マーケティング戦略の即戦力となるアンケートを実施される際には、是非こうした選択肢もご検討ください!
スキャン代行でペーパーレス化する3つのメリット
こんにちは、久保です。
大量の紙資料をバインダなどに入れ、
保管されている企業も多いかと思いますが、
今回は、そうした書類をすべてスキャンして、
ペーパーレス化するメリットについてご紹介いたします。
「回収したアンケート用紙が大量に放置されている…」
「調査票に記載されたお客様情報をまとめる時間がない…」
「社内資料を確認しに、保管庫へ行くのが面倒…」
「いつも持ち歩いている資料が重たくて困っている」
スキャン代行でペーパーレス化すれば、
こうした悩みをすぐに解消することができます!
各種書類のスキャンをご検討中の方は、
まず下記のメリットをご覧ください。
お客様アンケート実施のプロセスとメリット
こんにちは、木村です。
今日は、お客様アンケート実施のプロセスと
メリットについて考えてみましょう。
お客様アンケートの真意は、
「現時点での顧客の満足度を調査し、
その結果に基づいて
これから顧客満足度をより高めるための施策につなげる」
ことにあると言えるでしょう。
漫然とアンケートを行うのではなく、
実施プロセスの段階で
「得た結果をふまえどう動くか」を考えることが
非常に大切になります。
・目的を定める
(結果から何を知りたいのか)
・アンケート形式を決める
(Webか紙か、選択式か記述式か)
・集計結果の活用法
(内部資料とするか、公表するかなど)
最低限でもこの3つは
事前に明確にしておきましょう。
お客様アンケートの場合は
顧客属性によるリスト化などで
データの説得力が増すため、
設問内である程度の顧客情報は得ておきましょう。
とはいえ、お客様アンケートは
単に顧客管理のためにだけに行うのではありません。
時代や情勢によって移り変わる
顧客の満足度やニーズを、
その都度把握できるというメリットがあるのです。
Webを活用すれば、短期間で広範囲の調査ができ
結果のデータ化もスムーズに行えます。
顧客満足度を常に把握し、向上をめざすなら
アンケートの定期的な実施と回収は
大きな意味を持つことでしょう。