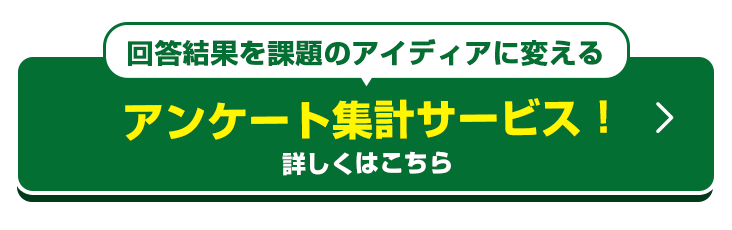イベントでアンケートを行う際のポイント
こんにちは、森田です。
セミナーや展示会をはじめとしたイベントを
無事終わらせるためには、
実に多種多様な、それでいて細やかな配慮が
必要となる業務がいくつも発生します。
中でも、イベントを運営する上で、
アンケート調査は欠かせません。
アンケートで得られる情報は、
実際にイベントに参加したお客様の生の声です。
それらは運営体制の改善、見込み客への
フォローアップやリード育成など、
幅広く活用することができます。
このように、様々な場面で効果的に活用できる
アンケートですが、有用なアンケートを
つくるためにはどうしたら良いでしょうか?
今回は、イベントにおいて、
アンケート効果を高めるために気をつけるべき
ポイントを紹介します。
ブランド戦略でアンケートを効果的に使う方法
こんにちは、森田です。
買い物をする際、デザインや値段、機能など、
決め手となる条件は様々です。
では、仮にそうした条件が同じ商品が並んでいた場合、
何を基準に選ぶでしょうか?
人によっては、
「このメーカーなら信頼できる」「〇〇製のものが好き」
といった理由で購入を決める方もいるでしょう。
そうした信頼感や愛着といった、
企業や商品に抱くイメージが「ブランド」です。
ブランドイメージが良ければ、選ばれる可能性は高くなります。
反対に、ブランドイメージが悪いと、
どれだけ優れた商品でも選ばれにくいでしょう。
それだけ、「ブランド」には価値があるのです。
ブランドの価値を築くためには、マーケティングを行ない、
ブランド戦略を練る必要があります。
効果的なブランド戦略を打ち出すためには、
アンケートを行ない購買層の好みや関心を知るなど、
実際に消費者の意見を取り入れることが効果的です。
そこで今回は、ブランド戦略で
アンケートを効果的に使う方法をご紹介します。
アンケート実施時に必要なサンプル数は?信憑性のある人数とは
こんにちは、久保です。
皆さんはアンケートを作成・実施する際、「調査する人数(サンプル数)」を意識していますか?
アンケートでは、一般的に対象となる「母集団」の中から一部を抽出して調査を行います。
それにあたり、「何人分集めたらいいのかわからない」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
サンプル数が少なすぎると、誤差が大きくなり、データの信ぴょう性が薄くなってしまいます。
サンプル数は多ければ多いほど、より正確なデータを集めることができます。
しかし一方では、コストがかさむだけでなく回収したアンケートの入力・集計に手間がかかるといったデメリットも。
本記事では、アンケートを実施するにあたっての適切なサンプル数について解説していきたいと思います。
関連記事:アンケート結果の効率的なまとめ方|パワポとワードのメリット・デメリットも解説
サンプル数は母集団の規模によって決まる
たとえば「ラーメンが好きな日本人」を調査したい場合、母集団は「日本人」となり、対象人数は約1億3,000万人です。
また、ある町内会の会員に意見の聞き取りをしたい場合は、その町内会の会員全員が対象となります。
当然、それぞれのアンケートで集めるべきサンプル数は異なります。
なぜなら母集団の規模がまったく違うからです。
以下に、上下5パーセントの誤差範囲で調査する際に必要なサンプル数(人数)を掲載します。
・母集団:100人⇒サンプル数:約80人
・母集団:1,000人⇒サンプル数:約280人
・母集団:10,000人⇒サンプル数:約370人
・母集団:100,000人⇒サンプル数:約380人
・母集団:1,000,000人⇒サンプル数:約385人
母集団が多ければ多いほど必要なサンプル数は増えますが、必ずしも母集団の人数に比例するわけではありません。
特に、母集団が10,000人以上になると、サンプル数の増加が緩やかになっていくのがわかると思います。
母集団が10,000人以上の場合、およそ400人のサンプルを集めることができれば充分だといえるでしょう。
関連記事:セミナーアンケートを有意義なものにする7つのコツを紹介!
アンケートの誤差を測る2つの指標
本来、100%正確なアンケート調査を行うためには母集団の全員に聞き取りを行うことが必要ですが、現実的にそれは不可能に近いです。
そのため、得られた結果には必ず「誤差」が生じます。
この「誤差」の程度を測る指標として、「許容誤差」「信頼レベル」の2つが存在します。
許容誤差
アンケートから得られた結果が、母集団の実態からどれほど離れている可能性があるかを表す指標です。
つまりこの数値が大きいほど、「実態からかけ離れている」ことを意味します。
仮に許容誤差が3パーセントだとして、「日本人の90%がラーメン好き」という
結果が得られたとき、実際の母集団は「87~93%がラーメン好き」ということになります。
信頼レベル
サンプルの中から選んだ1つが許容誤差内の結果である確率を表す指標です。
例として「信頼レベル90%」であれば、「100人中90人は許容誤差内の結果だった」ことを意味します。
一般的に、許容誤差は1~10%、信頼レベルは90~99%で設定されます。
アンケート入力・集計はプロセス・マネジメントにお任せ
アンケート結果は、正確なものでなければ有用なデータとして扱うことはできません。
信ぴょう性の低いデータを基に開発・改善を行ったところで、顧客が真に求める商品・サービスを提供することは難しいでしょう。
つまり、回収業務(サンプルを集めること)はアンケートを実施するにあたりきわめて重要な要素なのです。
回収後はただちに回答を入力、データ化し、戦略ツールとして役立てましょう。
「回答を集計・データ化する時間がない…」
「社内スタッフに入力を任せると入力精度が低い…」
このようなお悩みを抱えているお客様は、ぜひ弊社にご依頼ください。
入力精度99パーセント、顧客満足度90パーセントの実績で、お客様のニーズに速やかにお応えします。
従業員満足度(ES)アンケート作成のポイント
こんにちは、森田です。
「顧客満足度調査」という言葉はよく耳にしますが、
従業員を対象とした「従業員満足度調査」は
ご存知でしょうか?
会社方針、福利厚生、上司や同僚への満足度などを
調べることで問題点の洗い出し・改善を行うための調査で、
別名、ES(Employee Satisfaction)調査とも呼ばれます。
従業員の抱える問題やストレスが軽減されれば
会社への帰属意識の向上、ひいては
離職率の低下や社内の連携強化にもつながります。
今回は、従業員満足度を正確に測るために
重要なポイントについて、ご説明します。
研修の後は、アンケートで効果測定を!
こんにちは、久保です。
新人研修やスキルアップ研修などを実施した際、
終了後にアンケートをとっていますか?
研修をただ機械的に行うだけでは、参加者に知識やスキルは
身につきませんし、研修の質を上げることもできません。
特に、社外の会議室などを押さえ、著名な講師に講義を
依頼している場合は、講師料に見合う内容でなければ
費用対効果の悪い研修となってしまいます。
研修後のアンケートは、社内外を問わず非常に効果的です。
なぜなら、参加者の「熱」が冷めないうちに
意見を集めることで、より次回に活かせる情報が
得られるからです。
今回は、研修後の効果的なアンケート方法について
ご紹介します。
展示会でのアンケート実施のポイント
こんにちは、森田です。
商品・サービスの売上向上や顧客獲得のために行われる
展示会ですが、今後のアプローチをうまくすすめるためにも
「展示会でのアンケート」は重要です。
展示会でアンケートを行うことは、
展示会を成功させるための重要項目と言っても
過言ではありません。
では、展示会ではどのようなアンケートを
行えば良いのでしょうか?
そのポイントを分かりやすくご説明させていただきます。
高精度なアンケートの設計方法
こんにちは、久保です。
効率的なマーケティング手法の一つとして認知されている
アンケート調査ですが、本当に必要な情報を
入手しようと思うと、なかなか簡単ではありません。
「思ったほど、情報を入手できなかった」
「欲しいデータを得るために
必要なアンケート項目が分からない」
「アンケート調査の正しい進め方を知らない」
など、これまでアンケート調査で困ったことがある方も
多いのではないでしょうか。
アンケート調査には、必ず考えなければならない大前提と
決めなければならない7つの項目が存在します。
確実に効果を実感できるアンケート調査を行うために、
下記のポイントをご確認ください。
DMの効果測定方法について
こんにちは、久保です。
これまでの記事で、DM(ダイレクトメール)の
メリット・デメリットや
作り方のコツなどについてご紹介してきました。
ですがDMは「作って送ったら終わり」ではありません。
むしろ、そこから成約率や売り上げの向上に
つなげていくことが目的なのです。
そのためにも、送付後の反響を調べることは非常に大切です。
今回は、DMの効果測定方法についてご紹介しましょう。
(さらに…)
顧客満足度調査アンケート実施のポイント
こんにちは、森田です。
「顧客満足度調査」はアンケートの中でも、活用次第で
会社の業績アップに大きくつながる重要な調査です。
実施の大きな目的は「既存顧客の維持と、囲い込み」。
つまり、調査結果を反映させることにより、
商品のリピートや店舗への再来店を増やすことを
狙いとする企業様がほとんどだと思います。
商品・サービスの現状を把握・分析し、品質向上に役立つ
アンケートを作成するようにしましょう。
文書管理を成功させるための要点とは?
こんにちは、森田です。
年度末が近づき、書類の整理や保管体制の見直しを
お考えの企業様も多いのではないでしょうか。
文書を上手に管理するためには、
押さえておくべきポイントがあります。
倉庫整理やオフィスでの座席の移動に伴って
文書を整理する際は、古い書類を移動・廃棄して、後々
「あの書類はどこに置いたっけ…」とならないように
注意しましょう。