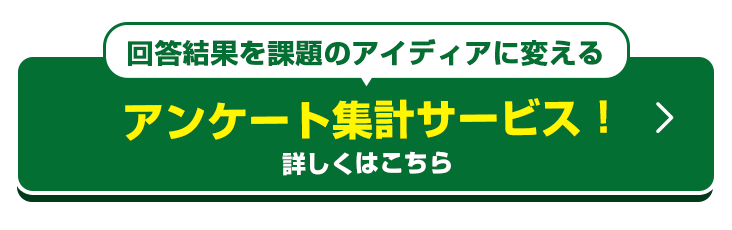アンケートにおけるレポート作成のコツ
こんにちは、森田です。
アンケートの集計結果をレポートとして作成する際、
「データをどのように可視化すれば良いのか?」
「集計結果を正確に、わかりやすくまとめるには?」
と悩むことはございませんか?
アンケートにおける報告レポートの完成度は、
集計にかかっているといっても過言ではありません。
そこで今回は、アンケート結果の効率的な集計方法と、
レポート作成のポイントについてご紹介いたします。
アンケートは紙とWeb、どちらが良い?
こんにちは、久保です。
アンケートを実施するときに
紙とWebのどちらで実施するべきか、
迷ったことはありませんか?
例えば、アプリの利用者やECサイトの購入者などを
対象としたアンケートであれば、
Webが適しているのは明らかです。
では、セミナーや展示会などでは、
紙とWebのどちらを用いた方が、効果的に
アンケートを実施することができるのでしょうか?
今回のブログでは、
紙とWebそれぞれの特徴をまとめ、
アンケートを実施するシーンごとに適した媒体をご紹介します。
アンケート配布・回収・集計時のポイント
こんにちは、森田です。
早いもので2017年最後の更新となりました。
これまで当ブログでは、DM発送やスキャニングなど
さまざまなことをご紹介してきましたが、
なかでも今年は、「アンケート調査」について
注力させていただきました。
読者の方はもうお分かりかもしれませんが、
アンケートを実施するときに重要なポイントは
配布・回収・集計です。
そこで今回は、
「アンケートの配布・回収・集計時のポイントや注意点」
をご紹介したいと思います。
アンケート結果を効果的に活用する方法
こんにちは、久保です。
一般的にいう「アンケート」とは
調査票を使った調査全般のことを指しますが、
手法やまとめ方にはたくさんの種類があります。
方法次第で、集計するデータの質は
大きく左右されるでしょう。
今回は、質のよいデータを収集し、かつ
アンケート結果を効率的に活用するために
参考にしてほしいポイントをご紹介します。
リッカート尺度はなぜ使われる?|上手な作り方とポイントについても解説
こんにちは、森田です。
「顧客からの評価を知るためのアンケート」に掲載する質問の、回答形式を考えるとき、「はい」「いいえ」で答えてもらうようにするのか?
あるいは複数の選択肢を用意したほうがよいのか?など、悩むことも少なくないものです。
効果的なアンケートにするためには、回答方式も適切なものにしなければなりません。
そこで本記事では、マーケティング調査で幅広く使われ、とりわけ人の態度や行動を調べたいときに信頼度の高い評価方法である「リッカート尺度」についてご紹介します。
関連記事:アンケート結果の効率的なまとめ方|パワポとワードのメリット・デメリットも解説
◆リッカート尺度とは◆
リッカート尺度は、心理的な傾向を測定する「尺度」のひとつです。
耳なじみがないかもしれませんが、アンケートでは頻繁に取り入れられている回答形式です。
回答者は、項目に対しての賛否度を数段階の選択肢の中から選んで答えていきます。
「はい」「いいえ」で答えられる質問とは異なり、質問項目に対して、「当てはまる」「どちらでもない」「当てはまらない」など、好意的~非好意的な選択肢を用意することで、反応の尺度を明確にすることができます。
◆リッカート尺度の使い方と作成ポイント◆
リッカート尺度は、満足度、有効性、可能性、頻度のいずれを測定する場合にも有効で、たとえば、下記のような使い方をします。
設問例
お客様にとってマッサージはどれほど重要でしょうか?
・極めて重要である
・とても重要である
・どちらともいえない
・あまり重要ではない
・まったく重要ではない
ここでは、中間的な選択肢「どちらともいえない」に対して、「まったく重要ではない」から「極めて重要である」という二極の範囲を示した選択肢を用意して、サービスに関する顧客の認識を測定します。
回答作成ポイント
次に、これらの回答を作るときのポイントを見ていきましょう。
言葉で表現する
尺度の測定なので、「<1~5>などの数値で測定することが適切」と思われるかもしれません。
しかし、数値は人によって感覚が異なり、混乱を招くため、尺度を計れるような「言葉」で表現することが好ましいです。
奇数のスケールにする
中間となる選択肢が必要なため、尺度の段階は奇数とします。
また、調査によると、7段階を超える尺度で意見を示すことは難しいということが明らかになっているため、「5段階評定」が一般的です。
単極の尺度を使う
「極めて健康」から「極めて病弱」のような反対の言葉の尺度ではなく、「極めて健康」から「まったく健康でない」のような単極の尺度で表現をしたほうが回答者にとって分かりやすいので、適切な回答を得られるでしょう。
その他のポイントとしては、
・尺度の段階は、包括的で均等を保った設定する(必ずどれかの選択肢に当てはまるようにする)
・質問は「同意文」を使用するのではなく、疑問文にする(「同意する/しない」といった選択肢だと、人は「同意する」を選ぶ傾向にあるため)
など、回答者を混乱させず、スムーズに考えてもらえるよう配慮すると、より有効な回答を得られるでしょう。
◆アンケートの入力・集計は弊社にお任せ!◆
今回の内容をお役立ていただければ、特定の態度や行動に関しての方向性、弱み・強みなどが手早く理解できる、有効な調査を実施できるようになるでしょう。
アンケート調査は、顧客満足度や商品・サービスの現状を知ることができ、今後の方針を左右する重要なものです。
そのため、ただ調査するだけでなく、集まった情報をいかに有効活用するかがカギとなります。
「集計したアンケートをデータ化したい」
「回答者の情報をデータ管理したい」
「アンケート結果を報告書にまとめたい」
などお考えの方は、弊社までお気軽にご相談ください。
アンケートの前に必要な「仮説構築」について
こんにちは、久保です。
マーケティングにおいて、
アンケート調査は有効な手段です。
その際たびたび見られるのは、
「ただ聞きたいことを並べた」だけのアンケートです。
回答を有効に活用したいと思っていても、
聞きたいことを並べただけでは、
「本音」の回答を得ることは難しいかもしれません。
では、本音を引き出せるアンケートを作るには
どうしたらよいのでしょうか?
参考となるのが、「仮説構築」という作業です。
そこで今回のブログでは、
アンケート調査の前に必要な「仮説構築」について
ご紹介したいと思います。
(さらに…)
アンケート結果の効率的なまとめ方|パワポとワードのメリット・デメリットも解説
こんにちは、森田です。
アンケート調査および集計が終わってからのまとめとして、多くの場合は、報告書の作成が必要となります。
さて、皆さまは「アンケート調査報告書」と聞いて、そこにはどのような情報が載っているとイメージするでしょうか?
「集計結果の記録」
「グラフ」
「調査結果を利用した分析」など
報告書のイメージは人それぞれかと思います。それはデータの用途によって異なるからです。
事前に報告する形式を明確にしておいたほうが、アンケート結果はまとめやすくなり、より目的に準じた報告書を作成できるでしょう。
そこで本記事では、アンケート結果を効率的にまとめるための「調査報告書のまとめ方」についてご紹介いたします。
「目的」から報告書のスタイルをイメージ
アンケート調査を行ったのは、「目的」があったからだと思います。
同様に、報告書も目的からイメージすると作りやすいでしょう。
アンケート調査報告書の基本は、「調査結果を忠実に記録し、伝えること」です。
したがって、下記のような目的からまとめられると思います。
パターン1:調査の記録
「どのような調査をして、どのような結果になったのか」
アンケート結果を記録したもので、もっともシンプルなまとめ方です。
調査結果を正確に記述することが重要なので、間違えた受け取られ方をされないよう配慮することが必要です。
この場合、誰が見ても分かるようにまとめることがポイントです。
パターン2:結果の分析
調査結果のグラフ・表を機軸にしてコメントなどをつけていく、一般的なアンケート調査結果のまとめ方です。
パターン1の「調査の記録」と同じように、コメントは結果から導かれた客観的な内容であることが望ましいです。加えて、その結果から導かれる分析をします。
ここで重要なのは、調査のまとめ(コメント)は客観的な内容のみとし、それに基づく分析のページなどは別に作成すること。
グラフ・表とコメントのみで分析をするのが難しければ、アンケート結果を基にした仮説なども記載します。
パターン3:調査結果+α
上記の2パターンとは異なり、アンケートの調査結果から導かれるものに加えて、他の情報や分析を織り込んでいくまとめ方です。
例えば、企業の立ち上げ時などにその事業の需要を調査したい場合、自社の情報や同業他社の情報などを加え、アンケート調査の結果と併せて分析するようなケースです。
この場合は、アンケート調査結果以外の情報も一緒に報告書にまとめる必要があります。
作成形式も「目的」から決定
次に、作成する手段もイメージしておきましょう。まずは、以下の2つから決めていきます。
・ソフトは文書作成用かプレゼン用か
・カラーかモノクロか
ここで、「アンケートのまとめには表計算ソフトが便利では?」と考えた人も少なくないでしょう。
表計算ソフトは文字の調整に労力を要することや、パソコンの環境による変化が激しいといった理由から汎用性に優れず、最近ではあまり利用されていません。
アンケート調査報告書の作成に向いており、実際によく利用されているソフトは、Microsoft(R) Word(R)かMicrosoft(R) PowerPoint(R)です。
では、これらのメリットとデメリットを確認していきましょう。
●Microsoft(R) Word(R)
<メリット>
・文書としてのまとめやすさがダントツ
・円グラフ、棒グラフ、折れ線グラフなども作れる
・スムーズに図表番号を追加できるなど
・冊子にする場合にも便利な機能が多い
・基本ソフトであるため共有しやすい
<デメリット>
・一部のグラフが作成できない
●Microsoft(R) PowerPoint(R)
<メリット>
・グラフを中心にした報告書作成に最適
・プレゼンなどに使用することも簡単
<デメリット>
・長い文書には適していない
などが挙げられます。
次にカラーかモノクロかですが、色を使えば分かりやすくなり、単純に見た目が美しいため、カラーでの作成が人気です。
カラーのデメリットは、印刷する場合にコストが高くなることぐらいなので、印刷時のコストメリットを考えた場合のみモノクロが優先的に選ばれているようです。
以上のメリット・デメリットをふまえて、アンケート結果のまとめ方を決めていくとよいでしょう。
アンケートの集計はプロセス・マネジメントにお任せください
パターン3としてご紹介した「アンケートの調査結果だけではなく、他の情報を織り込みながら分析を必要とする場合」などは、自社の強みなどを再度明確にしておく必要があります。
何よりアンケート結果は、正確なものでなければ有用なデータとして扱うことはできません。
たくさんの回答を集めても、信ぴょう性の低いデータを基にしては参考にならないからです。
つまり、回収業務(サンプルの収集)はアンケートを実施するにあたり非常に重要な要素なのです。
「回答を集計・データ化する時間がない…」
「社内スタッフは別の作業もあり手が足りていない…」
このようなお悩みを抱えているご担当者さまは、ぜひ弊社にご依頼ください。
まとめ
アンケート調査の報告書にもパターンがあるので、どんなふうに報告するかを明確にして、それにふさわしいスタイルで作成することが大切です。
業者などに委託する場合でも、同様のことを念頭に置いておくと、効率が上がるのでおすすめです。
※Microsoft Word、PowerPointは、米国Microsoft Corp.の登録商標です。
アンケートの選択肢は、「範囲」にご注意を
こんにちは、久保です。
皆さんはアンケートを作る際、
「選択肢の範囲」について気をつけていますか?
アンケートの回答形式はさまざまですが、
あらかじめ選択肢を用意して、回答者に選んでもらう形式を
「プリコード法」といいます。
このプリコード法は
「回答者の負担が少ない」「集計がしやすい」
など多くのメリットがあり
アンケートではよく用いられていますが、
適切な選択肢を設けなければ
正確なデータを得ることができず、
アンケートそのものが無駄になってしまう恐れがあります。
今回のコラムでは、効率良く、正確なデータを集めるために、
「選択肢の範囲の決め方」についてご紹介します。
販促にアンケートを活用する方法
こんにちは、久保です。
突然ですが、下記のような場面で
アンケートを受けたことはありませんか?
・飲食店で食事をしたとき
・ショップの会員になった後
・イベントやセミナーに参加したとき
・通信販売やゲームなどオンライン上で …etc.
アンケートに回答する機会は日常にあふれています。
つまり、企業側からすれば
さまざまな場面で実施できるアンケートは、
お客様のリアルな声を得るための有効な調査手段
といえるでしょう。
今回は、販促活動において
アンケートを有効活用する方法ご紹介します。
アンケート調査票の構成方法
こんにちは、久保です。
アンケートを行う場合に必要となるのが、
「調査票」と呼ばれるシート。
この調査票の完成度で得られるデータの良し悪しは
大きく異なります。
いざ調査票を作成してみると思いのほか難しく、
「回答率がふるわなかった」
「想像とは違う調査結果になってしまった」
という経験のある方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、効果的な調査票を構成するポイントを
ご紹介します。