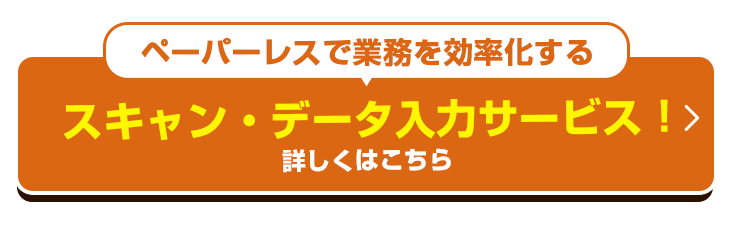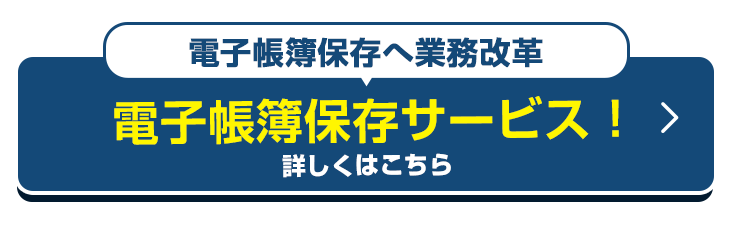紙の書類をデータ化するための方法は?データ化に成功した事例もご紹介
電子帳簿保存法の影響もあり、近年では企業が保有する紙の書類をデータ化する動きが活発になっています。
しかし、書類をデータ化する方法は多岐にわたり用途に応じて使い分ける必要があるため、「自社で全て対応するのは大変」と頭を抱える方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで本記事では、紙の書類をデータ化するためにはどのような方法があるのか、そしてデータ化するための基本的な流れを解説します。
あわせて、「書類が多くて対応しきれない」「やってみたけどミスが多くて困っている」といった方に向けて、データ化を外部委託することで得られるメリットもご紹介するので、書類のデータ化を推進したいとお考えの方はぜひ参考にしてください。
目次
紙の書類をデータ化する方法は?基本的な手順と機器ごとの特徴を比較
書類をデータ化する代表的な方法として、スキャナーとOCRの活用が挙げられます。
基本的な手順、そしてスキャナー・複合機・スマートフォンアプリそれぞれの違いを解説します。
スキャンとOCRで書類をデータ化する基本的な手順
スキャナーとOCRで書類をデータ化する場合は、主に以下の手順に沿って作業を進めます。
1.事前準備
はじめに、事前準備としてスキャナーで読み取る書類を整理します。
読み取る書類を分別することはもちろん、書類を留めているクリップやホチキスの針なども取り外しておきましょう。
事前準備を怠ってしまうと、スキャナーで読み込むために多くの時間を要したり、フィーダーと呼ばれる書類を一枚一枚送り込む装置にクリップやホチキスの針が挟まって、紙詰まりや故障の原因になります。
2.スキャニング作業
事前準備が完了したら、書類をスキャナーで読み取るスキャニング作業に移行します。
このとき注意していただきたいのが、スキャンの解像度を適切に設定しておくことです。
スキャナーによっても解像度は異なりますが、一般的な書類や本をデータ化するのであれば300dpi程度が目安となります。
また、書類の文字が小さかったり、細かな図表やイラストなどが含まれている場合には400dpi〜600dpi程度の解像度が理想的です。
さらに、OCR機能が備わったスキャナーを使用する場合には、書類を取り込む際に必ずOCRを適用する設定にしておきましょう。
3.スキャンデータのチェック・修正
スキャニング作業が完了したら、ファイルを開いて正しく書類が取り込まれているかを確認します。
スキャニング作業の際に書類が曲がっていると一部が見切れている可能性もあるため、そのような場合には再取り込みが必要です。
また、スキャナーの解像度が低すぎると文字が不鮮明になり、OCRでの読み取りができなくなることもあります。
4.保存
スキャンデータが正しく取り込まれていることを確認したら、名前をつけてファイルを保存します。
このとき、どの書類をどのファイルに格納したか分からなくなることも多いため、すぐに内容を把握できるよう格納場所やファイル名のルールを明確に定めておくようにしましょう。
スキャナー・複合機・スマートフォンアプリの使い方と機能の違い
一口にスキャナーといっても、スキャニングに特化した専用スキャナーや、コピーやFAXなどの機能も備わった複合機、スマートフォンのカメラで撮影するだけで取り込めるアプリなどがあります。
それぞれの使い方の特徴や機能の違いを一覧にまとめました。
| 専用スキャナー | 複合機 | スマートフォンアプリ | |
| 使い方 | PCに直接接続して使用 | ネットワークに接続し複数人で使用も可能 | スマホのカメラで撮影 |
| 機能 | スキャニングのみOCR内蔵の機種も存在する。 ADF(自動原稿送り装置)対応の機種は大量の書類も連続読み取りが可能。 高解像度・高画質の機種もある。 | スキャニングのほか、コピーやFAXにも対応OCR内蔵の機種も存在する。 ADF(自動原稿送り装置)対応の機種は大量の書類も連続読み取りが可能。 | 原則、スキャニングのみに対応。 OCR内蔵のアプリも存在する。 |
| 特徴 | シンプルな操作性と高解像度がメリット。 複合機に比べると安価でメンテナンスの手間がほとんどない。 | スキャニング以外にも機能が充実している。 オフィスでの利用に最適データの共有がしやすい。 | 大掛かりな装置が不要で手軽に使うことができる。 無料で使えるアプリも豊富で導入コスト・運用コストが安価。 |
紙の書類をデータ化するメリット
紙の書類をデータ化すると聞くと、面倒に感じられる方は少なくありません。
しかし、データ化をすることにより、企業に対して次のようなメリットをもたらします。
コスト削減
書類を紙のまま管理している場合、書類のやり取りで必要となる通信費、ファイリング用品の用意やメンテナンスなどの維持管理費用が必要となります。
しかし、データ化することによってやり取りの通信費やファイリング用品の購入費用などを大幅に削減することができます。
仮に、新たなスキャナーを導入することで一時的なコストがかかったとしても、長期的に見れば事務コストを抑えられ、予算の有効活用が可能になります。
検索性・業務効率の向上
デジタル化した書類はキーワード検索やAIを活用した自動分類が可能であり、必要な情報を瞬時に抽出できるという大きなメリットがあります。
書類の所在確認に費やす時間を大幅に短縮できるほか、情報の二次利用やデータ分析もスムーズになり全体の生産性が飛躍的に向上します。
保管スペースの削減
書類のデータ化によって物理的な保管が不要になると、キャビネットや書庫、倉庫などの保管スペースが不要になります。
それまで大量の書類を保管していたスペースを別の業務エリアや会議室、休憩スペースなどに転用でき、効率の良いオフィスレイアウトの最適化が可能です。
情報の紛失・劣化防止
紙の物理的な保管は火災や水害、盗難などによる消失リスク、経年劣化による変色・破損のリスクがあります。
しかし、デジタルデータはこのようなリスクがなく、定期的にバックアップをすることで中長期的に適切な保管をすることができます。
特に法務関係や税務関係、取引先との契約書など、厳重な管理が求められる重要書類の保管に適した方法といえるでしょう。
情報共有・リモートワーク対応
クラウド上にデジタルデータとして保存しておくと、ネットワーク経由で同時アクセスが可能です。
リモートワークが一般的な働き方として定着した昨今、書類のデータ化は合理的な管理方法の一つとなっています。
セキュリティ強化
物理的な書類の管理方法では、重要書類の紛失や盗難などによる情報漏洩のリスクがあります。
しかし、データ化した書類にアクセス権限を設定して部外者の閲覧を制限したり、ログ管理によって誰がいつアクセスしたのかを管理したりすることにより、データを安全に保管することができます。
また、暗号化など高度なセキュリティ対策も施せるため、サイバー攻撃による情報漏洩リスクも最小限に抑えられます。
紙の書類をデータ化する際の注意点
書類のデータ化は非常に便利で業務の効率化も期待できる一方で、さまざまなリスクも潜んでいます。
データ化をする際に特に注意しておきたい3つのポイントをご紹介します。
書類データの情報漏洩リスクがある
物理的な紙に比べ、データによる書類管理はセキュリティ強化につながりますが、情報漏洩リスクがゼロというわけではありません。
セキュリティ対策が不十分な場合はサイバー攻撃の標的となり、機密情報が社外へ流出するリスクがあります。
書類をデータ化して管理する場合はネットワーク機器やアプリへのアクセス権限を厳格に管理し、保存先サーバーやクラウドは必ず暗号化するようにしましょう。
また、万が一端末を紛失した際に備え、リモートワイプや自動ロック機能を有効化しておくことも大切です。
書類をデータ化する際のOCR処理で誤認識や変換ミスが起きる可能性がある
AIの発達によりOCRの認識精度は高まっていますが100%ということではなく、たとえば紙面の汚れや文字のフォントによる誤認識が起こる場合があります。
実際にOCRを活用しているユーザーの9割以上が誤認識の経験があると回答しており、重要書類をデータ化する際には二重チェック体制を構築しておくことが重要です。
電子帳簿保存法に対応しているか
電子帳簿保存法の改正により、2024年1月以降、電子取引での税務関係書類は紙による保存ではなくデータによる保存が義務化されました。
特に、スキャンしたデータを保存する際は改ざん防止のためのタイムスタンプ付与や検索要件を満たすデータ登録が必須となっています。
そのため、紙のデータ化を行う際のシステムは国税庁が指定する要件(解像度・保存期間など)に対応しているか、あらかじめ仕様を確認し社内規定にも反映しておきましょう。
【業種別】紙の書類をデータ化して成功したモデルケース
紙のデータ化を推進したくても、どのような業務に取り入れれば良いのか分からないという企業も少なくありません。
そこで、実際にデータ化に取り組み成功した事例をいくつかご紹介します。
【医療機関】電子カルテの導入
医療業界では長年、紙のカルテを物理的に管理するケースがほとんどでした。
しかし、患者の数が膨大になるとカルテを探し出すのに時間がかかり、特に一刻を争う場合に処置が遅れるケースもありました。
そこで、紙のカルテをデータ化し電子カルテに移行することで、患者の情報や過去の治療履歴なども瞬時に検索し、スピーディーかつ適切な処置ができるようになりました。
【物流・運送業】点検記録の電子化・クラウド化
国内外での海上輸送を手掛ける企業は、安全な船舶の航行を実現するためにそれまで紙で管理していた点検記録をデータ化し、クラウド保存へと移行しました。
これにより点検記録のリアルタイム共有が可能になり、トラブルが発生した際の対処や原因究明にも素早く対処できるようになりました。
今後はさらにDX化を推進し、配乗管理※や船員の育成にも積極的に取り組んでいくとしています。
※船に船員を割り当てて、雇用や健康状態の管理などを行う業務
【製造業】データ一元化による業務プロセスの標準化
製造業は、生産する製品によって業務プロセスが異なり、各部門が独自のマニュアルを作成・管理しているというケースが少なくありません。
しかし、このような運用では業務プロセスのムダに気づきにくく、生産性が上がらない原因にもなります。
そこで、ある大手電機メーカーはDX化の一環として業務プロセスやコード・マスタをデータで一元管理し、業務プロセスの標準化に取り組んでいます。
一元管理することで業務のムダに気づきやすくなっただけでなく、客観的なデータを経営戦略にも活かせるようになりました。
【小売業】店長会議の資料をデータ化
全国に数百店舗を展開する大手小売業者では、定期的に全店の店長が参加する会議を実施しており、そのたびに会議資料を印刷し配布するという手間がかかっていました。
そこで、タブレット端末を用いた会議のペーパーレス化に踏み切り、毎月6万枚におよぶ印刷コストの削減に成功。
さらに、従来は印刷コスト削減のためにモノクロ印刷で1枚の書類に情報を詰め込むなどのルールがありましたが、ペーパーレス化後はそのような必要もなくなり、資料作成の自由度も増したといいます。
【官公庁・自治体】電子決済システムによるペーパーレス化
官公庁や自治体には日々さまざまな申請・届出書類が集まり、その多くが紙でやり取りされていました。
しかし、昨今ではスピーディーな意思決定とコスト削減、住民の利便性向上などを目的としてデジタル化が進んでいます。
自治体によってデジタル化の進捗率は異なりますが、すでに半数以上の申請業務をデジタルに置き換えたり、押印を原則廃止にするケースも少なくありません。
書類のデータ化を外部委託するメリットと注意点
紙のデータ化は自社で行うこともできますが、膨大な量を処理するとなると多くの時間と手間がかかります。
そこで、外部の専門業者に紙のデータ化を委託することも検討してみてはいかがでしょうか。
書類のデータ化を外部委託することによって得られるメリットと注意点をご紹介します。
費用対効果が高い
自社にスキャナーや複合機などがあれば内製化することも可能ですが、書類の量が多かったり作業に慣れていなかったりするとデータ化に時間を要し、本来の業務に支障をきたしてしまうケースは少なくありません。
しかし、データ化を外部委託することによって自社従業員をコア業務へ専念させ、生産性を高めることが可能です。
また、書類のデータ化を専門とする業者は多くのノウハウを蓄積しているため、書類の見やすさはもちろん、ニーズに合ったファイル形式にしてもらうことができます。
最終的には、自社で行うよりも早く・正確に・適切なデータにすることができるため、費用対効果の高い方法といえます。
書類のデータ化サービスを利用する際の注意点
外部委託のコストを抑えることは企業として当然のことですが、やっすさだけを売りにしている場合は思わぬ落とし穴がある場合もあります。
必ず取引実績や対応可能範囲を確認し、安心して任せられる業者へ依頼するようにしてください。
また、機密情報が含まれる契約書や個人情報が記載された申込書を扱う場合には、情報漏えいを防ぐためのセキュリティ対策が万全であるかも重要なポイントとなります。
書類のデータ化はプロセス・マネジメントにお任せください!
私たちプロセス・マネジメントは、これまで大手企業や大学、研究機関など多くのお客様からご依頼いただいてきた豊富な実績による高品質への裏付けがございます。
また、Pマーク・DXマーク・ESGマークの第三者認証を取得しており、徹底したセキュリティ体制のもとで専任スタッフが対応させていただきます。
紙で保管してきた書類をデータ化し、時代の流れに沿った保管・管理を行いたいとお考えの方は、まずはお気軽にプロセス・マネジメントまでお問い合わせください。
まとめ
紙のデータ化は業務プロセスの効率化やミスの削減において重要な取り組みであり、持続的な経営に向けた投資の一環でもあります。
スキャナーや複合機があれば手軽に実践できますが、大量の書類がある場合は多くの時間や人的リソースを必要とします。
このような課題を解決し、効率よく紙の書類をデータ化したいとお考えの方は、ぜひ私たちプロセス・マネジメントへお問い合わせください。
豊富な実績と経験によって裏付けされた高品質な作業により、DX化の推進をサポートさせていただきます。